「精密医療」とは、最先端のゲノム医学を用いて細胞を遺伝子レベルで分析し、最適な薬を投与する医療のこと。国内では国立がん研究センター東病院によって全国270以上の医療機関が参加し、がんの精密医療の研究プロジェクト「スクラムジャパン」が進められている。
そのデータベースの構築や治験参加患者の橋渡しなどを行っているのが、土原一哉医師(顔写真)が分野長を務めるゲノムTR分野だ。
遺伝子を分析して、治療方針を探す従来の「個別化医療(テーラーメード医療)」と何が違うのか。
「がんは遺伝子が傷つき変異して起こるが、同じ臓器のがんでも数多くの遺伝子変異のタイプに分けられます。私たちが行っているのは、患者さんの『個別化』ではなく、がん細胞の遺伝子変異の『層別化』です。これを調べることで臓器別ではなく、遺伝子変異タイプ別の治療ができ、効く薬がなければ新薬の開発につなげています」
遺伝子の解析は、「NGS(次世代シーケンサー)」という最新の高性能機器で行われる。たとえば、肺がんでは「EGFR」「ALK」「ROS1」「RET」などの遺伝子に変異があり、現在、全体の4分の3くらいは分子標的薬のターゲットが見つかっているという。
「EGFR陽性の肺がんでステージⅣだと、従来の抗がん剤では余命1年とされていました。それが第1世代のEGFR阻害薬の『イレッサ』『タルセバ』が開発され、余命が2~3年に延び、それが効かなくなっても第3世代の『タグリッソ』を使うと、さらに余命が1~2年延びます。このように完全に治らなくても新薬が開発されるごとに余命が1~2年延びます。それに分子標的薬は副作用が少なく、飲み薬なのでQOLを保ちながら生活ができるのです」
■もともとは消化器外科医でスタート
薬が効かなくなるのは、がん細胞が耐性をつくるために、さらに遺伝子を変異させるからだ。しかし、遺伝子変異のタイプを層別化することで、耐性がどのようなメカニズムでつくられるのかも調べられるようになるという。また、ゲノム医学を用いた検査、診断法も大きく進歩してきている。
「がん細胞の遺伝子分析をするには、現状では生検でがん細胞を採取しなくてはいけません。患者さんの侵襲も少なくなく、部位によって必ずしも取れるとは限りません。それで血液検査で遺伝子異常のタイプを調べる研究が進んでいます。血液中には壊れたがんのDNAが含まれていて、100タイプくらいの遺伝子異常が分かります。この検査は、肺がんの一部では保険適用になっています」
土原医師は、もともとは消化器外科医でスタートしたが、臨床医として当時のがん治療の限界を感じた。手術しても、抗がん剤を使ってもダメ、どうしたら進行がんが治るのか。
それで肝炎のゲノムの研究をしようと、大学院に進学したのが基礎研究の道に進むきっかけだったという。
「この10年で精密医療の恩恵が最も大きいのは肺がんです。その成果を他の臓器のがんにもどんどん応用していきたいと思います」
△石川県出身。1993年金沢大学医学部卒後、同大付属病院研修医。2000年東京医科歯科大学大学院を修了し、オンタリオがん研究所(カナダ)研究員。国立がん研究センター東病院臨床開発センター、早期・探索臨床研究センターのTR分野長を務め、15年から現職。〈所属学会〉日本癌学会、日本臨床腫瘍学会、日本分子生物学会など。
気鋭の医師 注目の医療
遺伝子変異からがんのタイプを見分け創薬や治療に役立てる
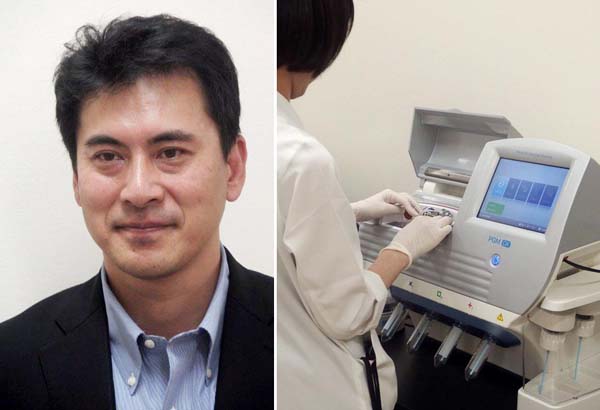
国立がん研究センター先端医療開発センター・土原一哉ゲノムTR分野長