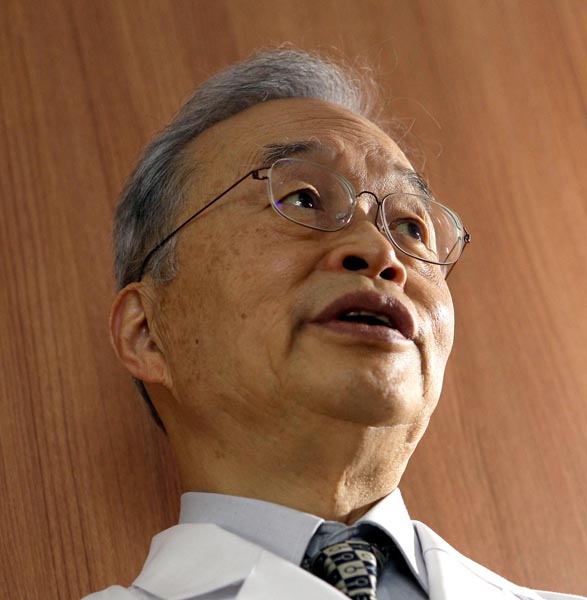不動産業を営むRさん(58歳・男性)は、喫煙歴40年になります。家族からも同僚からも「肺がんになっても知らないよ」と何度も注意されましたが、「どうせ、俺はがんか心筋梗塞で死ぬ。たばこなしの人生なんて考えられない」と言って、たばこはやめませんでした。Rさんは「仕事は十分にやった。人生も楽しんだ。いつ、死がやって来ても悔いはない。何があっても覚悟はできている。5歳のかわいい孫と別れるのがつらいだけだ」と考えていたのです。 また、ある医師の著書に「現代人はいつまでも生きる気でいる。死をもっと考えるべきだ。命に限りがあることをもっと自覚すべきだ。死を考えていないから諦めが悪い。死の教育が必要だ。この高齢社会で死生観の確立が必要だ」と書かれているのを目にして、同感したといいます。
「死なない人間なんていない。みんな死ぬんだ。俺は死なんて怖くない。太く短く、立派に死んでやる」
そんなRさんに、嗄声(声のかすれ)、咳、痰といった症状が表れ、3カ月ほど続きました。Rさんは「喉が荒れただけだろう」と思っていましたが、痰に少し血が混じり始め、妻から診察を受けるように勧められました。深刻に考えることもなく近所の耳鼻科を受診したところ、「左の頚部に硬いしこりがあります。紹介状を書くのでA病院を受診してください」と言われたのです。
翌日、A病院を訪ねたRさんは、担当の内科医から採血と胸部X線検査を受けるように指示され、その後でCT検査も行いました。そして、2時間ほど待ってから受けた診察で医師からこう告げられました。
「肺がんです。首のリンパ節と肺の中にも転移があり、手術はできません。来週、入院してもらって、気管支鏡を使った組織検査をしましょう。この検査はがんの確定と、どの種類の抗がん剤を使うかを決めるために大切です」
Rさんは、自分のスマートフォンに「肺がん 手術できない」といったワードを打ち込み、ネット検索してみました。すると、「余命1年」と書かれてあるサイトが目につきました。
「とうとう来たか。俺は1年で死ぬんだな。1年か……」
Rさんの頭の中では「1年」という数字が巡ったといいます。
■「誰だって生きたいのは当たり前」と言われて緊張がほぐれた
入院後に始まった抗がん剤治療ではつらい嘔気が2日ほど続きましたが、それでもRさんは繰り返しがんばりました。しかし、嗄声、咳、痰は良くなりません。2カ月すぎた頃に再びCT検査を行うと、医師から「いまの抗がん剤は効いていないので、治療薬を替えましょう。このスピードでは、もしかしたら3カ月の命かもしれません」と告げられました。
「3カ月」という数字がRさんの心にズシンと響きました。急に病院の廊下、待合室の景色が違って見え、空気が変わってしまったような気がしたといいます。このまま病院にはいられない気がして、急いで帰宅したそうです。Rさんは、自宅に帰ってからも何か落ち着かなくなっている自分に気づきました。
「あれほど『覚悟はできている』と思っていた俺はどこに行ってしまったんだ。3カ月後に俺は死ぬ。誰だっていつかは死ぬ。それなのに、俺はどうしたんだ。何が怖いんだ……」
2種類目の抗がん剤の点滴を受ける時、Rさんは一方の腕で震えを抑えながら、注射をしてくれる医師に「覚悟はできているつもりですが、どうしてあと3カ月の命なのに抗がん剤をやるのですか?」と尋ねました。すると、40歳代と思われるその医師からこう言われたそうです。
「3カ月と決まったわけではないでしょう? 抗がん剤が効いたらもっと生きられますよ。誰だって生きたいのは当たり前じゃないですか。きっと効きますよ。一緒にがんばりましょう!」
自分の目を見てそう言ってくれた医師の言葉を聞いて、Rさんは頭の中で何かが光ったような気がしました。
「医者が『きっと効く』と言った。ウソか本当かは分からないが、それでも『きっと効く』と言ってくれる医者がいる。誰だって生きたいのは当たり前か……。そうか、それでいいのか」
Rさんはホッとして、体の緊張がほぐれた気がしたそうです。
次回もRさんのお話を続けます。
がんと向き合い生きていく
「覚悟はできている」と考えていた患者が3カ月の命だと告げられて考えたこと