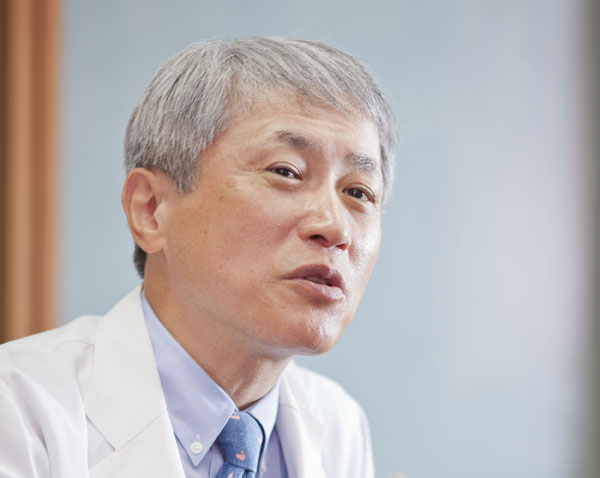外科手術は、「その方法でなければ機能を取り戻せない、健康を回復できない」といった病状に対し、エビデンス(科学的根拠)にのっとって行われるのが大前提です。その前提に加え、近年は「低侵襲」という方向性がクローズアップされています。手術の負担を軽減し、より患者さんの体にやさしい方法を推し進める流れが強くなっているのです。
その基本になるのが「メスで切開してできた傷をきちんと治す」ということです。「傷を治す」=「創傷治癒」は外科医にとっての原点といえます。
かつては、「主要な部分だけをしっかり処置して機能を改善できれば、傷は大きくても化膿して開かなければいい」くらいに考えられていました。しかし、化膿しないまでも手術の傷からいつまでもしみ出しがあったり、時間がたって大丈夫だと思った頃に傷の下にある骨が感染症を起こし、重症化して患者を亡くす経験などから、「傷もしっかり治さなければいけないのではないか」と考えていました。そこで、亀田総合病院に在籍していた20年ほど前から創傷治癒に対して真剣に取り組み始め、今に至っています。
「傷口を隙間なく確実に、あまり時間をかけずに縫合する」という仕上げの正確さを追求することはもちろん、人間の傷が治るメカニズムを見直して、創傷治癒を促進させる処置にたどり着きました。術中に傷口周辺の皮膚の皮下層にドレーン(誘導管)を挿入して吸引ポンプで陰圧をかける方法です。この方法は以前の“教科書”では行うべきではない処置とされていました。
現在、私が勤めている順天堂医院では感染症をほぼなくすことができているのも、術後の傷が圧倒的にきれいな治り方をするのも、「傷を治す」という原点に立ち返ったことがベースになっています。医師の中には傷を治すことを専門にしているエキスパートがいます。彼らのような専門家と同等以上にわれわれも学術的な研究について勉強を重ね、成果を上げている方法を取り入れていけば、より良い結果を出すことができるのです。
傷をできる限りきれいに治すことにおいて、切開や縫合の方法による違いはそれほど大きくはありません。基本的な手技さえしっかりしていれば、問題はないといえます。これまで大きく切開して処置していたところを、しっかり操作できる範囲内でできる限り小さく切開するといった工夫はしていますが、丁寧になりすぎたり、操作しづらくなって逆に時間がかかってしまうと本末転倒です。自分の技量との兼ね合いを考慮しなければなりません。
■自分の中に「鉄板」といえる型があるかも重要
また、外科医は自分の中で「こういう形で仕上がれば鉄板だ」と思える“型”を持っているかどうかも重要です。患者の血管の太さや心臓の大きさなど、全体のバランスが自分の中の「鉄板」に近い型に仕上げることができれば、機能の回復はもちろん傷もしっかり治ります。そうした自分の中の「鉄板の型」をしっかりイメージできていれば、それに向かってより速く正確に仕上げることを追い求めていく。そしてそれが、患者には長期の安定と併せて大きなプラスになります。
ほかにも、傷をきれいに治すための医療材料がかなりよくなりました。体の組織に近いバイオマテリアル(生体材料)からつくられた創傷被覆材や縫合糸もそうですし、人工血管や人工弁も進歩しています。
以前は、アメリカ人向けの大きなサイズのものをそのまま仕方なく日本人を手術する際にも使っていましたが、いまは同じメーカーでもアメリカ版、日本版、アジア版といったように数種類がラインアップされるようになりました。
外科医も医療メーカーも、「傷をきちんと治す」という原点をおろそかにしていると生き残れない時代になっていくのではないでしょうか。
天皇の執刀医「心臓病はここまで治せる」
「傷を治す」外科医の原点に立ち返えれば患者の負担も軽減できる