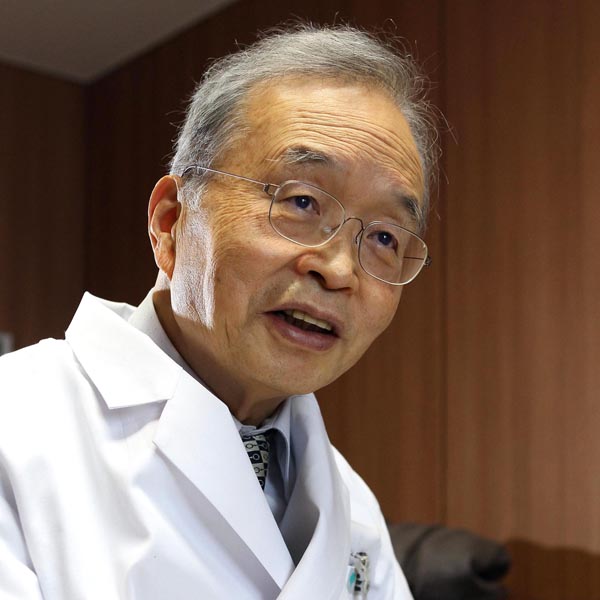元公務員のSさん(68歳・男性)は妻のKさん(66歳)と2人暮らしで、2人の子供(娘30歳、息子28歳)は仕事が忙しいのか、ほとんど家には帰ってきませんでした。
4年前、Kさんは咳と嗄声、嚥下困難があり、近所の医院で肺がんと診断されました。すぐにがん専門病院で手術が行われ、続いて化学療法、放射線治療を受けました。しかし、治療後も嗄声、嚥下障害が残り、その後、嚥下性肺炎で2度入院。さらにその2年後には脳梗塞を患い、左半身麻痺が起こってしまったのです。
Sさんは、Kさんの介護と家事を一手に引き受けて頑張りました。そんな夏のある日、Kさんが急な発熱と呼吸困難を起こし、手術を受けた病院に救急搬送されました。担当医から「嚥下性肺炎で、がんの再発ではありません。入院して抗生剤で様子を見ましょう」と告げられ、Sさんはホッとして帰宅しました。
しかし、翌朝の4時ごろに病院から「すぐに来るように」と電話が入り、Sさんは娘、息子に連絡して病院に駆け付けました。そして、当直医から「このままでは呼吸が止まります。血圧が下がって意識がはっきりしなくなっています。人工呼吸器をつけるか、このまま様子を見るか、どうしましょうか?」と問われたのです。
Sさんは「妻はずっと病気で苦労してきたから、安らかに眠らせてあげよう」と考え、「もう何もしなくて結構です」と言いかけました。しかし、息子は「先生、できるだけのことをお願いします」と人工呼吸器の使用を希望し、娘も「お願いします」と同意しました。そんな子供たちの言葉に、Sさんは何も言えなくなったそうです。
それを受けた医師は「それでは挿管し、人工呼吸器につなぎます。隣の部屋で少しお待ちください」と、すぐに処置に取り掛かりました。人工呼吸器につながれたKさんは、血圧は安定しましたが、鎮静剤の作用もあってか、意識がない状態が続きました。
Sさんが、そんな妻の状態を友人に話すと、こう言われました。
「だから元気な時に自分自身の希望を書いておく『事前指示書』が勧められているんだよ。自分なら、意識がない状態になったら人工呼吸器はいらない。蘇生もしない。自然のままでいい。そう書いておくよ。意識がない状態で、ずっと生かされたら最悪だよ」
Sさんはなるほどと思いました。しかし、意識なく横たわっているKさんを見ると、複雑な思いです。
■助かってよかった…
人工呼吸器をつないでから4日後、担当医から「血液の酸素の状態が良くなってきました」と伝えられ、7日後には「挿管の管は口から入れておくのに限界があります。喉の所に穴を開けて、そこから呼吸器につなぎます。気管切開です。その後、鎮静剤を減らしていきます」と言われました。
そして2週間後には肺炎は好転。救急蘇生室から一般病棟へ移り、人工呼吸器は外されました。しかし、Kさんの意識はもうろうとしていて、Sさんのこともはっきり分からない状態が数日続いたそうです。
ある日、Sさんを見つめるKさんに笑顔が見られました。その時、Sさんはこう思ったといいます。
「あの時、もし妻が書いた事前指示書があって、『人工呼吸器はつけない。いざというときは何もしない』と記されていたら、きっと息子も娘もそれを見て納得しただろうし、医師もそれを尊重して、人工呼吸器はつけなかったかもしれない。そうしたら、いまの妻の笑顔は見られなかっただろう。これからも生きるのは大変だけど、つらいことがいっぱいあるだろうけど、笑顔の妻が、いまここにいる。助かって良かった」
それでも、Sさんはこう考えました。
「妻の肺炎は不治ではなかったのだ。ただ、これがもし自分だったら、やっぱり人工呼吸器をつけるのは嫌だ。自分自身が書く事前指示書には『人工呼吸器は必要ない』と書いておこう」
次回もSさんのお話を続けます。
がんと向き合い生きていく
もし「人工呼吸器はつけない」と希望する事前指示書があったとしたら…