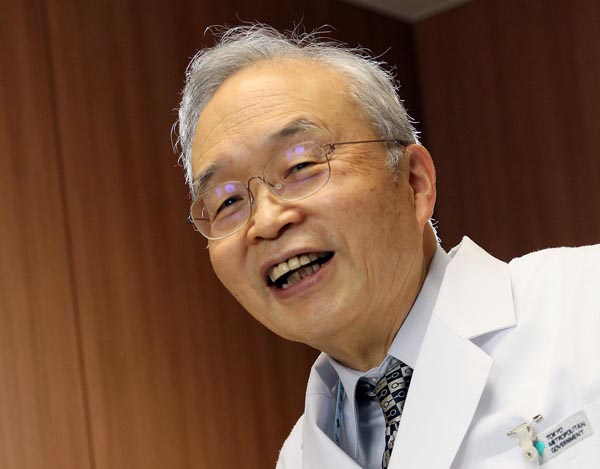古い話で恐縮ですが、われわれの病院での出来事です。
消化器内科のI医師は、かつて大学の研究室で犬を使った実験をしていた経験があります。「『採血だよ』って声をかけると、犬は前足を差し出す」と言うのです。犬にとって採血は痛いし、嫌なこと。信じられないような話ですが、彼はとても優しい心の持ち主なので、私は本当の話だと思いました。
消化器内科の胆・膵グループに赴任したI医師は、末期の膵臓がんなど治療ができないほど進んだ患者さんを受け持っていました。
1993年、お正月でも自宅に帰れない患者さん4人を集め、朝9時前の15分間ほど歌の会を始めました。動けない患者さんには、希望があれば病室に行って一緒に歌ったそうです。
その後、あちこちの病棟から患者さんが集まるようになりました。事務のAさんがその週に歌う4曲ほどの歌詞を印刷し、集まった方に配り、ウクレレで伴奏します。がん患者が多い病棟の廊下のコーナーの所で、月曜日から金曜日まで毎朝、患者さんの歌声が響くようになりました。そんな歌の会は、通算10年以上、2009年3月31日まで続きました。
朝8時半ごろから体操が始まり、45分から15分間歌います。いつも30人ほどの患者さんが集まっていました。ある週では歌詞を150部印刷しても足りないこともあったようです。
1995年末にI医師は故郷で開業することになりました。当時、化学療法科(現腫瘍内科)の部長だった私は、I医師から「この会を安心して続けるには、傍らに医師がいる必要がある」との相談を受け、歌が好きだったこともあってI医師の後を継ぎました。
歌の会は、毎週毎週続きました。福島県から来られたある男性の患者さんは食道がんで手術後の放射線治療で2回目の入院でした。以前、一緒だった患者さんと再会され、うれし涙を流しながら「ふるさと」を追加リクエストして歌っていました。
入院期間が長かった時代ですから、退院が決まったことへの喜びを表す方もいれば、同室で亡くなった方を鎮魂したり、点滴を引きずってエレベーターを乗り継いで参加される方など、一人一人の思いは違います。同じなのは皆さん歌が好きな方々でした。
ある時は患者さんの家族がプロ歌手で、朝早くに病院まで来て会に加わったこともありました。どこで聞きつけたのか、一度NHKのラジオで全国に放送されたり、ジャパンタイムズに英字で紹介されたこともあります。ある年の病院内のテーマ別改善運動発表会では、サークル名「早春賦」で最優秀賞に選ばれ、東京都衛生局から「特別賞」をいただきました。
■昔に比べていまは"良い医療”が行われているが……
時代は大きく変わって、大病院では包括診療報酬制度となり、多くの検査は外来で実施され、クリニカルパスというスケジュールに沿って治療が行われ、入院期間はとても短くなりました。
がん拠点病院では、相談支援センターや患者サポートセンターなどが設置されています。多くの病院でクリスマスコンサートなどのイベントが計画され、また、がん種によっては患者会などもできました。今は、あの時代に比べるとはるかに進んだ“良い医療”が行われているのです。
しかし、患者が中心となり、患者が自主的に集まって歌う会は他にはあまり聞きません。このような歌の会の復活はとても無理なのですが、何かとても大切なものを、大切な仲間を失ったような気がしています。
事務のAさんが「再開する時のために」と残してくれた歌詞集が今も私の手元にあります。「ノスタルジア」だと嘲笑されそうですが、「どこかで春が」「みかんの花咲く丘」「あざみの歌」「里の秋」など、偶然、知らない患者同士が一緒に歌った曲目は658曲に上ります。
あの頃、病気と闘い、泣いて、笑った「歌う仲間」がいたのです。
■本コラム書籍「がんと向き合い生きていく」(セブン&アイ出版)好評発売中
がんと向き合い生きていく
かつて患者が自主的に集まって合唱する「歌の会」があった