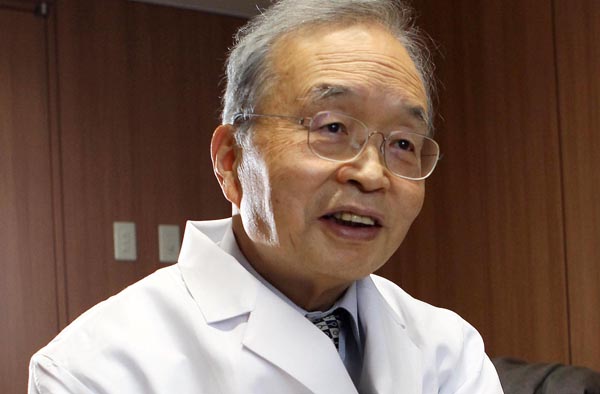桜が咲くと必ずAさん(当時34歳)という乳がんの患者さんを思い出します。
随分前のことになりますが、私が勤めていた病院の裏庭に桜の木が2本並んでありました。当時は毎年この時季になると、化学療法科(腫瘍内科)病棟の桜の花見の日を2週間ほど前に決めていました。そして、1週間ほど前から患者さんに花見をする希望を聞いておきます。桜の木の下へ花を見に行くことを、ほとんどの患者さんが希望されました。
日程が決まると、天気を心配し続けて当日を迎えます。その日だけは注射などの抗がん剤治療は午後に回しました。看護師は、この日はいっそう忙しく見え、いや、普段よりもっと生き生きと輝いているようでした。
その日は幸い晴れて、暖かい陽に恵まれました。午前10時から準備を始め、その後、患者さんの移動です。病院の裏庭にある桜の木の下に敷くシート、椅子、点滴架台などの運搬から、看護師と医師がカンパして買った飲み物、お団子、お菓子を運ぶことから始まりました。
点滴架台を引き連れて歩く患者さん、車椅子やストレッチャーで運ばれる患者さんなど、さまざまな格好で桜の木の下に集まります。シートに座った患者さんは40人ほど。裏庭の桜は、木の下から見上げても枝はわずかで、花も少ししかなかったのですが、皆さん喜んでくれたようでした。
Aさんも花見に行くことを希望されました。Aさんは大量の酸素吸入が必要だったため迷いましたが、直前になって少し顔色も良くなり、「桜のところへ行きたい」と言われ、即、連れて行くことを決心しました。
酸素吸入の音をたてながらストレッチャーに乗ったAさんを、医師と看護師みんなで桜が咲いている枝の真下、花が顔にかかるほどのところまで連れて行きました。Aさんは顔の真上の桜の花を見て、「きれい、きれい」と喜んでいます。
これまで、呼吸の苦しみやつらさでずっとこわばっていたAさんの顔から、こわばりがまったくなくなって、にっこりと幸せそのもののように見えました。一緒にAさんを運んだ看護師たちと私も、汗を拭きながらお互いにっこりと顔を見合わせました。
病気の進行は誰も止められません。苦しい、つらい中で、誰もその運命をどうすることもできないのですが、その中でも一瞬緊張が抜ける、一瞬でも幸せを感じることができる――。人間とは、こんなにつらい状況になってもそれが可能なのだと思わされました。
桜の枝を折って、Aさんと一緒に病室に戻りました。Aさんがあんなに喜ぶなら、もっとたくさんの花がある桜を見せたかったと思いました。
それから2日後、Aさんは亡くなりました。私は彼女の2人の子供に「お母さんの分まで、元気に生きるんだよ」と声をかけました。まだ小学生だった2人は、泣きながら「うん」と頭を縦に振りました。子供たちは桜の枝を持って、亡くなったお母さんと一緒に寝台車に乗り込みました。私はその日が勤務の看護師たちと一緒に礼をして見送りました。
今はもうあの桜の木はなくなり、広い駐車場に変わっています。私の手元には、シートに座った患者さんと一緒に撮った写真だけが残っています。現在の病院では、あの頃のような「時間」や「余暇」を持てるとはとても思えません。
最近は、患者と医師・看護師の人間関係が薄いと言われます。あれから医療はずっと進歩しました。しかし、患者と医師の人間関係は、告知や同意書の署名などで、かえって薄くなっている。そして、お互いに心のゆとりがなくなっているようにも思います。多くの医師も看護師もいずれ患者になるのに、信頼関係の構築はなかなか難しい時代になっている。そう感じさせられるのです。
■本コラム書籍「がんと向き合い生きていく」(セブン&アイ出版)好評発売中
がんと向き合い生きていく
桜の下で幸せそうに喜ぶ患者さんを見て思わされたこと