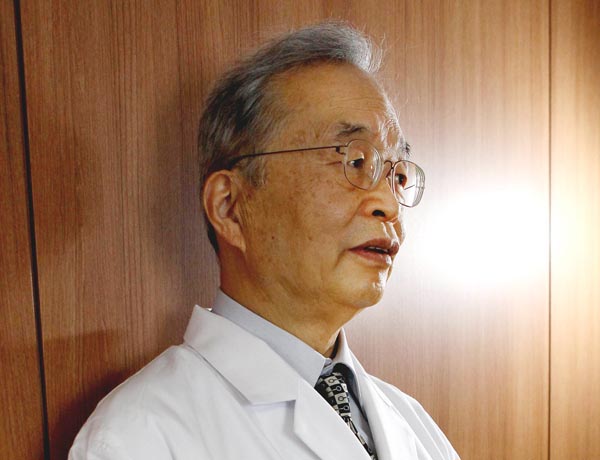肺がんや乳がんなどでがんが胸膜に進んだ場合、がん性胸膜炎を起こすことがあります。この場合、胸水といって胸膜に水がたまり、この水にはがん細胞がたくさん含まれています。
これと同じように、心臓を包む心膜にがんが及ぶとがん性心膜炎となり、心のう水がたまります。たくさんたまると心臓は圧迫されて拍動しにくくなり、命に関わります。多くの症状は呼吸困難や不整脈、そして胸がとても苦しくなります。
Nさん(48歳・女性)は、夫、高校生と中学生の娘の4人家族で仲良く暮らしていました。左乳がんの手術を受けたのが5年前で、その後、放射線治療、ホルモン療法などが行われました。
しかし、4年を過ぎた頃から左胸の手術の痕に赤くぼこぼこした小さな塊がたくさんできてきて、がんは再発し、胸水がたまるようになりました。骨シンチグラム検査では、全身の骨にがんの転移が見られましたが、骨折はなく、痛みもありませんでした。
抗がん剤の点滴治療で胸水は減り、小康状態となりました。しかしある日、呼吸困難と胸の苦しみを訴えて来院され、胸部エックス線写真では、胸水のほかに心臓の影が大きく拡大し、超音波検査で心のう水がたまっていることが分かり、緊急で入院されたのです。
循環器内科医にお願いして、心のう水を約150ミリリットル抜きました。心のう水は血液を抜いているのかと思うほど真っ赤でしたが、検査してみると静脈血よりもはるかに薄く、たくさんのがん細胞を認めました。抜いた後、苦しい症状はすぐに改善し、その後に径4ミリほどの細い管を留置して、注射液で溶かした抗がん剤を心のう内に注入しました。管からの排液は日に日に減り、赤みも少なくなりました。
Nさんは私にこう話されました。
「先生、早く家に帰りたいのです。私は子供たちに命が短いことを話してあります。家で、みんなに囲まれて安らかに死にたいのです」
しばらくして、Nさんは退院して外来通院となりました。経過は良く、さらに2回、心のうへの管から抗がん剤を注入した後、感染の危険から液がたまっていないのを確認して管を抜きました。 その後、約4カ月間は良好でした。しかし、5カ月目に入った頃、軽い息苦しさが表れました。胸部エックス線写真では、再度心陰影が大きくなり、心のう水がたまってきていました。
■自宅に帰る希望をかなえられなかった
私は「このままでは危ない。また心のうに管を入れて治療し、元気になろう」と入院を勧めました。しかし、Nさんは入院を嫌がって「家にいる」と言うのです。ただ、Nさんの自宅近くには往診してくれる医院は見つかりませんでした。
急に苦しくなった時、夜に救急車で病院に来ても、当直医は胸水なら抜けるが、心のう水を抜くのは専門の循環器医でないと難しいこと、心のう水で苦しい場合は酸素吸入では治まらないことなどを話して入院の説得を続け、やっと3日後に入院することになりました。Nさんは、同室の患者さんに「私は先生の言うことを聞いてあげたの。先生のために少しだけの入院なの」と話していたそうです。
ところが、入院後に心臓の働きが急激に悪化し、あらゆる治療にも回復せず、とうとう家に帰れないまま亡くなられました。がんの末期とはいえ、あれほど「家にいたい」と言っていたのに……。また良くなるためにと説得しての入院だったのに、家に帰る希望をかなえられませんでした。
私は「こんなことになるならぎりぎりまで家にいさせてあげたかった」と後悔しました。いまも私の頭の中には、「私は先生の言うことを聞いてあげたの。先生のために入院したの」というNさんの言葉が残っています。
同じ終末期でも、病状によってなかなか患者さんの希望通りにはいかない現実があるのです。
■本コラム書籍「がんと向き合い生きていく」(セブン&アイ出版)好評発売中
がんと向き合い生きていく
「心のう水」を抜くのは専門の循環器医でなければ難しい