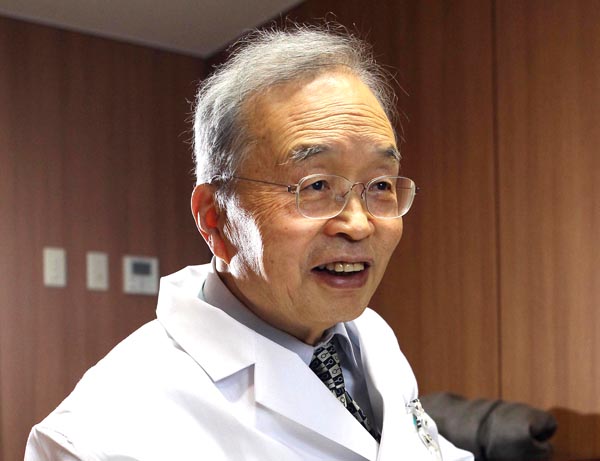少し前のことですが、ある複数の緩和病棟でとても気になることがありました。「標準化、効率化を最優先にしたのではないか」と思ったのです。
病院では「クリニカル・パス」(以下パス)というものが使われています。たとえば、あるがんの手術で入院した場合、同じ病期なら、同じ検査をして、同じ手術が行われ、同じ日程で退院するようなスケジュールが組まれたものです。これによって検査などの漏れがなくなり、患者にとっては前もって予定が分かります。標準化や効率化として良い方法のひとつだと思います。
こうしたパスのひとつとして、イギリスでは2003年ごろから一般病院やナーシングホームなどで、死が近い患者に対して「看取りのパス」(リバプール・ケア・パスウエー)が使われました。慣れていないケアを行う人のために、すべてを同じチェック項目で同じ手順とすることで、ケアの質を上げるというものです。
驚いたことに、日本ではこれが複数の緩和病棟で日本版「看取りのパス」として使われました。論文発表では看取りのパスは終末期の緩和医療標準化ツールのひとつで、その理念は「よりよい生の終焉(good death)を迎えるために……その道程となる標準的手法を提示」とあります。
終末期になって、一般状態の悪化や浮腫などの病状をチェックし、適応基準に合致すると看取りのパスに入るそうです。パスに入ると不要な治療・検査は中止され、標準化された終末のケアで患者ごとのケアのばらつきが減少するといいます。 麻薬などの鎮痛剤は残しながら、高カロリー輸液や抗生剤などの注射が削減され、その結果、薬剤費は半減。そして、看取りのパスを適応した場合、3日以内に亡くなった方が6割以上だったと報告されています。
■スタッフには迷いやためらいを捨ててほしくない
また、論文では「患者に『死について』話してもよいか? 家族はどう思っているかなど、スタッフは対応に不安があった。しかし、このパスにより、ほぼすべてのスタッフが迷い、ためらいといった消極的感情を捨てることができた」としています。
死亡3日前くらいの状況でパスに入るようですが、そのとき患者には「栄養、抗生剤の点滴をやめます」「パスに入ります」と告げるのでしょうか? インフォームドコンセントができているといっても、私は「患者の心は大丈夫なのだろうか?」ととても気になりました。
該当する緩和病棟を直接見たわけではないので、勝手なことは言えません。ただ、患者は死を受容していたとしても、きっと心の奥には「生きたい」という気持ちが残っていると思うのです。臨終期にあって、医療者には、生きていていいんだよという心、命を惜しむ心、別れの悲しみ、哀れを感じる心、未練を肯定する心があると思うのです。ですから、スタッフにはむしろ迷いやためらいを捨てて欲しくないと私は思います。
アメリカの精神科医で医療人類学者のアーサー・クライマンは、著書「病いの語り」の中でこう記しています。
「死を迎えるにあたって……ひとつの不変の道などないのである。……どのような方法が最良の選択なのかを、あらかじめ知ることはできない」
また、聖路加国際病院名誉院長で105歳で亡くなられた日野原重明先生は、「日本の生死観大全書」の中で「ホスピスでは……患者ひとりひとりに個別的にタッチするということが必要で、全体をまとめてマスとして扱うことはできません」と述べています。
実はイギリスでは、看取りのパスがまだ回復の余地がある患者にまで適応されたとの告発が続き、2014年に国として全面禁止したといいます。その後、日本でも看取りのパスの報告は見つからなくなりました。
死亡3日前からのケアの標準化とは、団体でベルトコンベヤーに一緒に載せられて死んでいく……そんなイメージが浮かんできて、私は賛成できないのです。
■本コラム書籍「がんと向き合い生きていく」(セブン&アイ出版)好評発売中