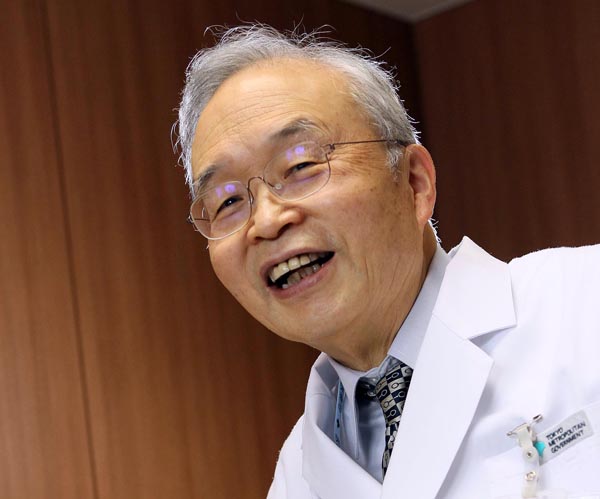私の友人だったRさん(58歳・男性=会社員)のお話です。
Aがん専門病院で胆のうがんの手術を受けたRさんは、その1年後、腹腔内にがんが再発し、抗がん剤治療のために短期間の入院を繰り返していました。
その時も短期入院の予定だったのですが、腹水が出てきて病気が悪化していることが分かりました。さらに、手術した部位の痛みが続いていて、食事は半分くらいしか取れず、痩せてきています。時々、咳き込むこともあり、「今後、自宅で過ごすのは無理ではないか」と判断され、自宅近くのB病院に転院を勧められました。
A病院の担当医は、「今はがんの積極的治療は無理です。体力が回復したらまた治療を考えましょう」と言ってくれたそうです。とはいえ、やんわりとした話だけだったこともあり、Rさんからしてみれば「助からない命、捨てられた命」と判断されたと感じたままの転院でした。
「こんなはずではなかったのに……。いつ退院できるか分からないB病院への転院で、今度は生きて帰れるのか? 地方で大学に通っている息子はどうしているだろうか。高校生の娘は来年受験だが、一緒に合格の喜びを味わうことは無理に違いない……」
B病院での病室は3階の4人部屋で、ベッドは窓際でした。夜、窓からは大小のビル群と窓の明かりが見え、ビルの下には線路が通っていました。走ってくる電車の窓から乗客の姿が見えます。一人一人の表情までは分かりませんが、立っている人、座っている人の影は確認できました。そんな景色を目にしながら、Rさんは考えたそうです。
「家路につくあの人たちは、死からは遠い“安全圏”の人だ。自分は死に近い捕らわれの身……。何も悪いことはしていないのに捕らわれの身なんだ」
朝になると、看護助手が床頭台を拭きにやって来ます。優しい医師や看護師が来てくれても、“捕らわれの身”には変わりありません。売店に行くにも検査室に行くにも、ナースステーションで許可を得ないと病室を出られないのです。
◇ ◇ ◇
朝、カーテンを開けると曇り空で、ビル群にまだ人の動きはない。
以前、手術が終わってA病院を退院した時は、病院で支払いを済ませてから建物の外へ出て、クルマが行き交うビル群の下を健康な人たちと一緒になって歩道を歩いた。空は曇っていたが、とてもまぶしく、うれしかった。
「ああ、自由になれたんだ。シャバに出られたんだ。俺は笑って歩いている。おかしなヤツと思われるだろうが、そんなことはお構いなし。ああ、俺はシャバに出られたんだ」
あの時の、あの気分を自分はもう味わえないのだろうか?
◇ ◇ ◇
転院して最初に迎えた日曜日、Rさんは2時間だけの許可をもらって、普段着に着替えて近くのコーヒーショップに出かけました。
「入院中の捕らわれの身だということをだれも気付かないだろう。ただ、疲れた男が入ってきたとしか思わないだろう。でも、私は『2時間』に縛られた捕らわれの身なのだ。壁にかかったルノワールの絵も、店内で流れているドボルザークの新世界も、私には何も語らない……」
Rさんは、コーヒーを半分残してそそくさと病室に戻りました。
「外にいた人たちと私とは違う。私は捕らわれの身。死が近い身なのだ」
◇ ◇ ◇
働いているRさんの妻は、週2回ほど着替えを持って来てくれます。B病院に移って3週間がたった頃には、息子が訪ねて来てくれました。
男同士で何を話すか、Rさんは話題を探しました。息子は、病状を気遣っているふうもなく、いま学んでいる哲学の話をしてくれました。世の中で直接は役に立たない話だけれど、学んでいることを熱心に話す息子の姿に、「よし、大学の勉強はそれでいいんだ」とRさんは思ったといいます。
息子は、今の政治の批判も口にしていました。Rさんは自分の学生時代が蘇り、咳き込みながらも息子の成長をうれしく思ったそうです。
息子さんの話を聞かせてくれた時、Rさんは笑顔でした。きっと、死が近いこと、捕らわれの身だと感じていることも忘れていたのだと思います。
■本コラム書籍「がんと向き合い生きていく」(セブン&アイ出版)好評発売中
がんと向き合い生きていく
“捕らわれの身”と感じている友人が息子の話になると笑顔に