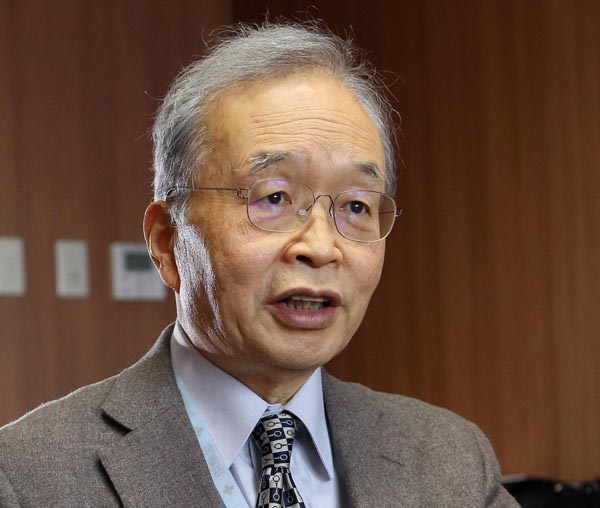Aさん(65歳・男性)は、B病院の守衛として20年間、60歳まで勤めました。55歳の時に悪性リンパ腫となり、勤務しているB病院で治療を受けているのですが、それでも何かにつけ自宅近くの診療所に出向いては、I先生に相談しています。AさんはI先生が一番の頼りで、信頼しているのです。
その診療所で、AさんはI先生にこんなお話をしたそうです。
「I先生、私のリンパ腫は、進行はゆっくりだけど完全には治りきらないタイプと聞いています。勤めていたB病院に6回も入院して、何種類も治療を受けて、担当医も何人か代わりました。今回も、若い担当医から『効いていたリツキサンが効かなくなりました。でも、リツキサンが効かなくなった場合に効く薬が出たので、その薬で治療をしましょう』と言われました。点滴だそうです。最初は入院かもしれない。それで、私は『もういいです。こんなに頑張ってきたので治療はしません』と言ってきました」
しかし、Aさんはその後になって考え直し、I先生に申し出ました。
「その薬が効くのであれば、この診療所、I先生のところでなら治療を受けたいと思います。B病院の担当医が嫌だからでもありません。ここで治療していただけたら、結果はどうであれ本望です」
Aさんのお話は続きます。
「私はB病院に入院するたびに『無駄な延命治療はしたくありません』と担当医に言ってきました。特に何を考えるわけでもなく、その治療で1、2カ月ほど命が延びる程度なら、副作用もあるだろうし、やりたくないという意味でした。どの担当医も『はい分かりました』と簡単に答えてくれました。私は病院の守衛ですから、ある時、知り合いの看護師に『先生は何か言っていましたか?』と聞くと、『いざ急変した時は、人工呼吸器をつけたり、救急蘇生はしないとの本人の希望があるとカルテに書いてありましたよ』と教えてくれました」
Aさんは自分の思いと担当医の受け取り方は違うのだと感じたそうです。それでも、そのままそれ以上のことは話さずに治療を受けてきたといいます。
「私はB病院で仕事をしていたことで、人工呼吸器につながれた患者さんをたくさん見てきました。それぞれの人生を歩まれ、意識はなくなっても手も体も温かい。見舞いに来られたご家族は『よろしくお願いします』と言って帰られます。患者さんが熱を出し、痰がたくさん出る時などは、医師や看護師は痰を吸引しやすいように一生懸命、背中を叩いたりして手当てをしていました。その患者さんたちを見て『無駄な延命』なんて思ったことはありません」
その一方、Aさんは自分が入院するたびに「無駄な延命はしたくありません」と言い続け、この治療が無駄だったのか、無駄でなかったのかを考えながら、10年間も生きてきたのです。
■「無駄な延命」なんてあるのだろうか
今回、勧められた新しい薬で治療することも、無駄な延命のような気もすると思いながら、長年まじめに仕事をしてきたから、また元気になって、好きな釣りに行くのも許されるのではないかとも思っているといいます。そして、さらにこう続けました。
「それにしても、自分で言っておいて変ですが、『無駄な延命』なんて誰が決めるのでしょうか。『無駄な延命』なんてあるのでしょうか? 『誰の命も尊く、無駄な命などはない』とよく言われます。結局、それでも私の結論は、一番心がすっきりするのはI先生のところで治療を受けて、I先生にお任せし、最後はI先生に看取ってもらう。私はI先生のもとでは無駄な延命も何もないのです。私は最後まで看てくれるI先生がいてくれて安心です。幸せです。大病院に行くつもりはありませんが、I先生が行くようにと言われたら行きます」
そしてAさんは、I先生に「先生、私、ずいぶん延命できたのだから、その分、死ぬ時は苦しいことはないよね」と言ったそうです。するとI先生は「え? え?」と、きょとんとしていたといいます。
きちんとした信頼関係が築けているからこそ、患者さんは思っていることを正直に口にできるのです。
■本コラム書籍「がんと向き合い生きていく」(セブン&アイ出版)好評発売中
がんと向き合い生きていく
「治療が無駄だったのか」を考えながら10年間も生きてきた