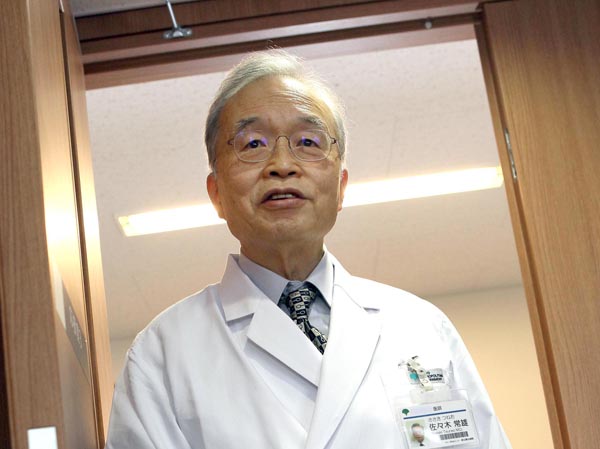2年前に膣からの出血が時々あったNさん(75歳・女性)は、自宅近くにあるB総合病院の婦人科で「進行した子宮がん」と診断され、手術、抗がん剤、放射線治療を受けました。
その後は小康状態でしたが、6カ月ほど前から下肢の浮腫が強くなってきて、歩くのも一苦労です。買い物などは隣町に住む娘さんに来てもらって済ませ、何とか一人暮らしを続けていました。
そんな中、1カ月ほど前からまた時々出血が見られるようになったので、娘さんと一緒にB病院の婦人科に行きました。そして、医師からこう言われたそうです。
「なかなか難しいね。今は出血は止まっているし、また出血で困ることがあったら来てください。治療はもう終わっているし、緩和ですね」
Nさんは、「緩和」と言われたことがとてもショックでした。がんに対する治療が終わっているのは仕方がないとしても、出血や下肢のむくみを何とかして欲しい。もし出血が止まらなくなったり、下肢のむくみがひどくなって象の足のようになったらどうしよう。歩くのが大変になってトイレに行けなくなったら……などと考えただけで怖くなってきました。
「何か方法はないものかね?」
Nさんが娘さんに尋ねると、インターネットで調べた娘さんからこんな提案がありました。
「お母さん、子宮がんにはどうか分からないけど、A病院に腫瘍内科というのがあって、そこでは新しい薬の治療ができるかもしれない。予約してみる。何か新しい方法があるかもしれないし、行ってみよう。B病院の婦人科で診療情報提供書を書いてもらうよ」
■希望や元気が出てくる
Nさんと娘さんは2週間後に、予約が取れたA病院まで電車とバスを乗り継いで足を運びました。診察した腫瘍内科医は診療情報提供書に目を通し、下肢のむくみを診てから言いました。
「残念ですが、ここではあなたの治療法はありません。これまで手術や抗がん剤の治療をしてきた婦人科で診てもらってください。私は婦人科医ではないので、出血も止められません」
ある程度は予想していた返事ではあったのですが、Nさんはがっかりして帰ることになりました。
道中のNさんはふらふらしてしまって、娘さんに支えられながら家に着きました。娘さんは「私の家で一緒に暮らそう」と言ってくれます。Nさんは「それも仕方ないかな」と思いながらも、その時は返事をしないでいました。
その後も出血が続き、下肢がとても重く感じて、3日後には娘さんの車でB病院に行きました。病院に着くとやはりふらついたので、玄関で車イスに乗って婦人科の外来を訪ねます。すると、婦人科の担当医から「出血を止めたいですね。無理だとは思いますが、もう一度、放射線科で治療できないか相談してみましょう」と提案があり、放射線科に連絡を入れてくれました。そして、「追加照射はあと7回なら出来ますよ。きっと止血すると思います」との回答があったのです。
その言葉だけで、Nさんは急に足が軽くなった気がしました。もう治療法はないと諦めかけていたのが、「まだ治療できる」「止血できる」というのです。
すぐにCT検査が行われ、放射線を当てる部位のシミュレーション(治療範囲の計画)をしてくれて、その日のうちに1回目の治療が開始されました。
新たな治療を受けた後の帰り道、Nさんは一人でしっかりと歩き、娘さんには「もう私一人でバスで病院に通って、あと6回治療を受けるよ」と伝えました。まだ方法があって、治療が始まった。希望が、元気が出てきたのです。
完全にがんをなくせる治療ではなくても、「治療法がある」という事実は患者にとってとても大切です。「治療法はなくなりました。緩和しかありません」――。医師から、そう淡々と告げられる患者がいます。そう言われた患者は、たとえどんなにつらくても、「分かりました」と平気そうに答えるしかないのです。医師には、「治療法がない」と言われる患者の心のつらさを思いやって欲しい。そう思います。
■本コラム書籍「がんと向き合い生きていく」(セブン&アイ出版)好評発売中
がんと向き合い生きていく
がんを根絶できなくても「治療法がある」という事実は大切