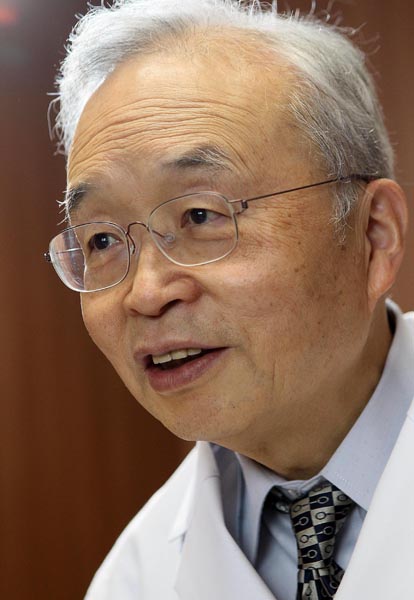会社員のSさん(43歳・女性)は、地方の女子高、首都圏にある短大の英語を学べる学科を卒業し、都内の商社に勤めました。それから数年でリストラに遭って辞め、新薬などの調査・統計を行っている小さな会社に再就職しました。
知人から紹介されて交際した男性はいましたが、特に引かれることもなく独身で過ごしています。親しい友人はなく、映画が好きで日曜日はひとりでよく出かけ、自分では洋画評論家になれると思っています。特に不自由を感じることもなく暮らしてきました。
農業を営んでいた両親は、60代で脳出血、心筋梗塞で亡くなりました。弟が家を継ぎ、結婚もして、田畑を見てくれています。
ある日、乳がんの検診で腫瘤を指摘され、病院受診を勧められました。すぐに、ある病院の乳腺外科で検査を受けたところ、腋窩リンパ節転移が疑われました。結局、右乳腺と腋窩リンパ節郭清の手術を受け、「大きさ3センチの乳がん、リンパ節転移があり、ステージⅡB」との診断でした。
手術後、傷痕を毎日シャワーで洗い流しました。鏡に映る自分の姿を見ていると、なんだか情けなくなって涙が出てきました。
退院後、Sさんはホルモン療法と抗がん剤治療を受けることになりました。抗がん剤は、3週間に1回、計4回行いました。「頭髪が抜ける」と言われたので、前もって短く切り揃えてウィッグを用意したのですが、さすがにバッサリ抜けてきたことには驚き、とても憂鬱になりました。しかも、ホルモン剤はこの先10年間も飲むのだそうです。
「今まで、人生で良かったことなんて何もなかった。勉強はクラスで中の上くらい。運動会ではいつもビリだったし、合唱コンクールは予選落ち……。結婚することもなく、子供もいない。そして乳がん。私の人生ってなんなのでしょう? 生まれてきたって仕方がない、意味のない人生なのかしら……」
会社からは抗がん剤治療が終わるまで4カ月間の休みをもらいました。
最後の抗がん剤治療が終わると、Sさんは弟に連絡して久しぶりに田舎に帰ってみました。お花を持って、弟が先祖代々のお墓に車で連れて行ってくれました。
お墓のそばにある桜はすでに咲き始めています。「乳がんはステージⅡBだから死ぬことはない。大丈夫」と思いながらも、手を合わせて心の中で父母にこう話しかけました。
「今度は私がそちらにお世話になりますので、よろしくお願いします」
■「見守っている」と言われている気がした
弟は、「久しぶりに裏山の風穴に行ってみるか?」と誘ってくれました。中学生の時に遠足で訪れて以来です。
山の方へ向かって約30分、途中、ユキヤナギの白い花が山道を飾っていました。車を降りてしばらく歩くと、一面、緑の大きなくぼ地があります。座って穴に顔を近づけると、風が吹いてくるのが分かりました。Sさんは手術した右側の手をかざして祈りました。
「この腕を清めてください!」
近くの山寺から町一面を見渡した後、山を下って帰りました。古い家に戻って仏間で一息つくと、欄間に掲げてある祖父、祖母、父、母の大きな写真が目に入ります。
おじいさんは川で泳ぎを教えてくれた。おばあさんは、ままごとで遊んでくれた。お父さんは私がいつも徒競走でビリになっても、親が参加する競技に出て1等になって私に賞品をくれた。お母さんはいつもお弁当をつくってくれた……。
「そうか、ご先祖さまがいて、そして私がいるんだ。みんながいてくれたから私がいて、そしてこれからの私もあるんだ」
そう思っていたら、写真のみんなが「あなたを見守っていますよ」と言ってくれているような気がしました。
4歳になる甥が「おばちゃーん、ゴハンですよー」と大きな声で叫ぶのが聞こえました。「はーい」と答えながら、Sさんは東京に戻ったら担当医に「いつ乳房再建の手術をするか」を相談しようと思いました。