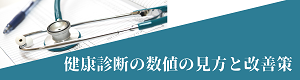新型コロナウイルス感染症の蔓延で、死を身近に感じる人が増えている。知り合いや著名人の感染が、自らの死生観について考えるきっかけとなっているのだ。そこで思い悩みたい。もし理想の最期を迎えることができるのならば、どんな形がいいのだろうか。
日本の少子高齢化は医療のあり方を変えている。政府は高齢者が地域で暮らし続けることができるように、在宅の医療・介護を推進。厚生労働省の患者調査の概況(2017年)によると、患者の平均在院日数も、この27年間で15~16日間も短縮された。
医療の進歩もあるだろう。実際、以前ならば入院していた患者でも、在宅で治療や療養を続けられることになった。
「在宅医療の対象となる患者は、介護が中心の寝たきりの高齢者で医療的な処置が少ない人というイメージを持たれる方が多いように思います。実際は、点滴や人工呼吸器など医療依存度が高い方も少なくないですし、これまで病院で行われてきた治療や処置を在宅で行うこともあります。今では急性期を脱した慢性期の患者も、在宅医療で対応できるようになってきているのです」
在宅緩和医療の第一人者が考える「理想の最期」