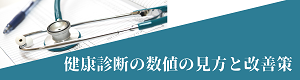「そう誤認している人は医療者にもいます。でも、モルヒネは正しく使うことで、それまでは痛みがあってできなかったベッドからの起き上がりはもちろん、自力でトイレ、食事をできるようになる方もいます。直前まで痛みを感じずに亡くなるケースも多いのです」
蘆野さんが使うモルヒネで、がん患者は痛みから解放された。しかし、入院患者からは「良くなったのに、なぜ自宅に帰れない」「帰れないならば、なぜほかの治療をしない」などの声が聞かれるようになった。
「がん告知はしない方がいいとされていた時代。患者は自分が何の病気か本当のことは知らないまま、亡くなってしまっていました」
残された時間に限りがあることを知らなかった人も多いだろう。
ならば最期は家族で一緒に過ごせるように自宅に帰してあげたい――。蘆野さんはそう思うようになっていった。当時は介護保険もなく、確立された在宅医療の制度もなかったが、幸運なことに、勤務先の病院が労働福祉事業団(現在の労働者健康福祉機構)の在宅医療プロジェクトに参加することになった。
蘆野さんは、これをきっかけに本格的に地域で在宅ターミナルケア(現在の在宅ホスピスケア)に取り組むことになる。
(取材・文=稲川美穂子)
在宅緩和医療の第一人者が考える「理想の最期」