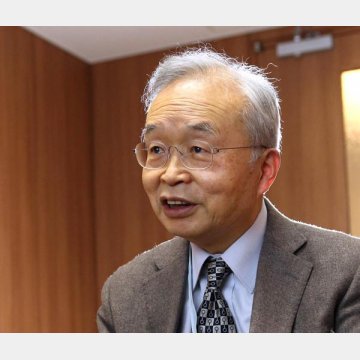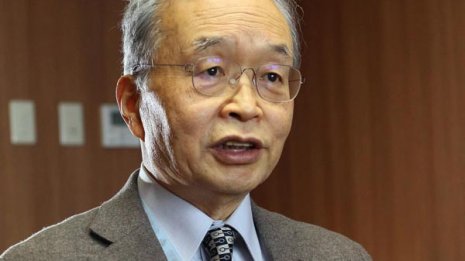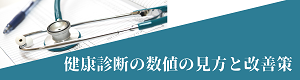Nさん(65歳・男性)は進行した肺がんで、Aがん専門病院に通院されていましたが、自宅が私の勤務している病院に近いとの理由で転院を希望して来院されました。
最初の診察で、Nさんと私はこんな話をしました。
「Aがん専門病院の担当医から、『胸水がたまってきてがんは悪化しています。当院で最期はみとりません』と言われました。先生、最期はここでみとってくれますか?」「ええ、いいですよ。でも、Aさんの治療はまだまだできますよ」
「ありがとうございます。これで安心しました。良かったです。みとってもらえないとすると、自分で首を吊って死なないといけません。これで安心しました。私には身内がいません。まったくの天涯孤独なのです」
その後、Nさんは胸水が増え、それをコントロールするために入院しました。その時、Nさんはこんな希望を話されました。
「先生、やっぱり自分の家が良いです。食事は出前で寿司も取れますし、ステレオで音楽をジャンジャンかけられるし、家に居るのがいいです。朝、昼、晩と食事が出て、体温と血圧を測って、おとなしくベッドにいるのは私には合いません」
さらにこんな会話を続けました。
「私はロッククライミングが大好きで60歳までやっていました。絶壁を登るのですから、とても気持ちが良くて、登り終わった時の達成感はとても素晴らしいものです。力を振り絞るというか、死んでもやり遂げるのです。落ちるという怖さはあります。危ないっていう不安もあります。だから魅力があるのです。一度、落ちて救急車で運ばれたことがあります。背中と腰をしたたか打ったのですが、大丈夫でした」「それでやめたのですか?」
「いえいえ、やめはしません。それからも5年ほど登りました。いやー、とっても楽しかったですよ。足を痛めてやめましたが、いまでもまた登りたいです。岩にへばりつくように咲く高山植物もいいですよ。あのコマクサ、知ってますか? かわいい花です。また会いたいです」
■死と向き合うことは生を豊かにする
Nさんのお話を聞いて、私は米国の精神科医、D・ヤーロムの言葉を思い出しました。
「死と向き合うことは、不安を引き起こすが、それはまた生を豊かにする可能性を秘めている」
まさにこのことを指しているのではないかと思ったのです。
人間は、スポーツ、たとえば100メートル走でもマラソンでも、限界まで頑張って、頑張って記録を更新します。そこに生きがいを感じるのだと思います。そういうことなのかな、と思いました。
80歳で3度目のエベレスト登頂に成功した登山家三浦雄一郎さんは次のように言っています。
「65歳でひどいメタボになり、糖尿病、狭心症、腎臓病でこのままでは人工透析になると言われ、身長165センチで体重は90キロあったが、それからの訓練だった」
エベレスト登頂ですから、この場合も死と向き合っているといえるでしょう。雄一郎さんの父である三浦敬三さんは、100歳になっても現役のプロスキーヤーで、指導者としてスキーの楽しさを伝えた方でした。90歳代になってもなお大滑降に挑戦されていました。 Nさんは、ロッククライミングの話をされた時、とても目が輝いていました。死の恐怖との隣り合わせ、そこに魅力を感じていたのだろうと思います。
私は毎日が病院の勤務で、それとはまったく異なる世界の話を、羨ましく、ずっと聞いていたいと思いました。
そういえば、私の同僚にバンジージャンプが好きな医師がいました。ただ、私はあれは好きになれません。なんであんなことをするのか、したいのか……私には気が知れません。
私が高校生の時、飛び込み用のプールで体育の先生から「ここから飛び込んだら単位をあげる」と言われたことがあります。でも、飛び込み台に立つと足が震えました。単位をもらうことも、死を考えることも何もありません。ただただ怖いだけで、意気地がなく、飛び込めませんでした。
Nさんや三浦さんが感じていた生きがいは、私にとってはやはり別世界のものなのかもしれません。
■本コラム書籍「がんと向き合い生きていく」(セブン&アイ出版)好評発売中
がんと向き合い生きていく