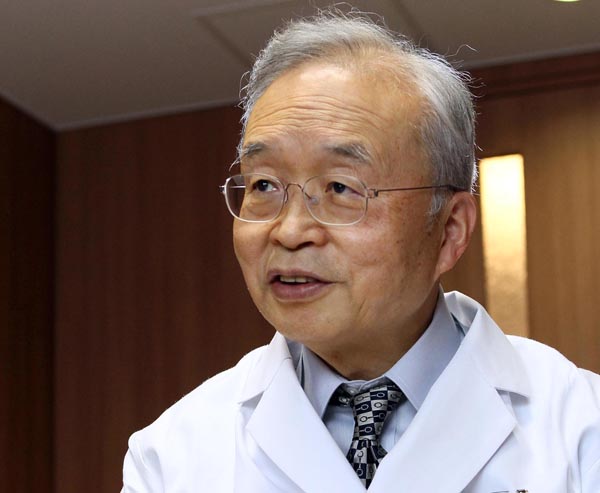患者さんが病院で亡くなった時、病理解剖(剖検)をお願いすることがあります。
「自分が死んだら、先生から解剖を依頼されると思う。そうしたら必ず応じるように。それが先生へのせめてもの恩返しだから」
ある患者さんはご家族にそう話しておられました。
私は担当したたくさんの患者さんに対して、病理解剖をさせていただきました。
ある患者さんが亡くなり、夜中に解剖が始まりました。その日の解剖当番のM先生は、日本の病理学の権威でした。M先生が述べる言葉を私は記録していきます。
「肝臓、重さ1200グラム。表面凹凸なくスムース、肝内胆管拡張なし……」
その最中にこう話しかけられました。
「佐々木君、この患者のがんは大変激しいがんだね。どんなに激しく転移していても、普通は脾臓にはなかなか転移はしないものだよ。この方は脾臓にもたくさん転移がある」
M先生が話されたような状態は医学の教科書にも載っていません。あとで調べてみると、剖検で脾臓に転移があったことだけでも論文発表がありました。それくらいまれなことなのです。
どうしてがんは脾臓に転移しにくいのか? 今もよく分かっていません。また転移しにくいだけではなく、脾臓は心臓と同様にがんの発生が少ない臓器です。脾臓も心臓も血流が多く、体の中では他の臓器よりも高温になっていて、がんは熱に弱いことが関係しているのではないかという説がありますが、これもよく分かっていないのです。
脾臓は腹部の左側にあり、大人では通常長径10センチほどの大きさです。成人の健康な人では、あまり問題にされない臓器ですが、脾臓の働きは4つあります。
(1)濾過機能:異物や老化した赤血球の捕捉・除去を行う。
(2)免疫学的機能:脾臓の中のリンパ小節でリンパ球が作られ、体の中に入ってきた細菌やウイルスと闘う抗体を作り、免疫に関する働きをする。
(3)貯蔵機能:正常人では赤血球の貯蔵作用はほとんどないが、右心不全や門脈圧亢進症では血液が高度に貯留する。このため、脾臓は大きな脾腫となる。
(4)造血機能:胎生期5カ月までは主に造血(赤血球、白血球、血小板)の主役で、生後は主としてBリンパ球、形質細胞を産生する以外、一般的には造血機能は観察されない。
■免疫機能が落ちるリスクがある
進行した胃がんの手術でのお話です。日本では、脾門部のリンパ節転移があり、胃全摘を必要とする患者では、リンパ節と脾臓の摘出も一緒に行うことで治癒が見られたため、脾摘は標準的な手術(D2郭清)、胃全摘術の一部と考えられてきました。しかし、リンパ節は切除しても脾摘が必要なのかどうかを検討するため、脾摘をする群と、脾臓を残す群との無作為(くじ引きのようにしてどちらに当たるか分からない)比較試験が行われました。
その結果、両群で全生存期間に差はなく、むしろ術後合併症の発生割合は脾摘群で多かったのです(30・3%対16・7%)。合併症の主なものは膵ろう、腹腔内膿瘍でした。しかし、術後の晩期合併症の発生割合は差がなく、全生存期間も両群に差はありませんでした。
結局、これまでの胃全摘標準手術の脾摘術群よりも、むしろ脾臓を残す群は安全性(合併症発生、出血)で優れ、脾臓は残した方が有効な治療法として、新しい標準治療となったのです。
また、がん以外でも脾臓を摘出する場合があります。治療に抵抗性を示す特発性血小板減少性紫斑病などの血液疾患や、門脈圧亢進症などでも行われます。脾臓は、生きていくためにどうしても必要な臓器というわけではありません。しかし、脾臓のない人はある人に比べ、肺炎で亡くなる人が多いとの報告もあり、脾臓を摘出した人は免疫機能が落ちて感染症のリスクが高いと考えるべきなのです。実際、脾臓を摘出した場合は肺炎球菌などの感染リスクが増すことから、ワクチンの接種が行われます。
脾臓にはまだ分かっていない重要な働きがあるかもしれません。
がんと向き合い生きていく
かつては摘出も…がんになりにくい「脾臓」は残した方がいい