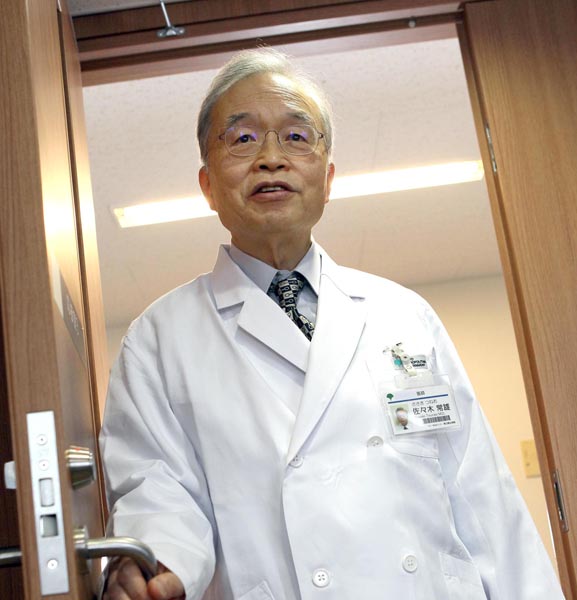病院の看護師寮に住んでいるAさん(28歳・女性)がこんなお話をしてくれました。
◇ ◇ ◇
私は看護学校を卒業後、ある病院の消化器内科病棟に勤務しました。入院患者の中には胃がん、大腸がん、膵臓がんが進行し、亡くなる方がたくさんいらっしゃいました。当時、私は夢中になって患者さんのために一生懸命がんばりました。担当した患者さんが亡くなった時は、遺族の方から「よくやってくださいました。ありがとうございました」といった感謝の言葉をしばしばいただきましたが、私自身は、夜ベッドに入ると亡くなった方を思い出し、「もっとやれることがあったのではないか」と反省を繰り返していました。
去年の春からコロナ病棟ができて、そこに勤務するよう命じられました。私は嫌とも思いませんでした。コロナへの対応については、政府もマスコミも「医療者に感謝」と繰り返し、ブルーインパルスが空に舞ったこともあります。しかし、コロナ病棟では、同僚がひとり、またひとり……と辞めていきました。
先月は、同じ病棟で一度に3人の看護師が職場を去っています。ひとりは出産で、ひとりはコロナ患者のいない病院へ移りました。もうひとりは、いったん看護師を辞めて故郷に帰るといいます。すぐに他の病棟から補充の看護師がやって来ましたが、コロナ病棟でのルールや感染防御について教えるのはいつも私の役目です。
一日の勤務が終わり、重い感染防護服を脱いで寮の部屋に戻ると緊張から解き放たれますが、とにかく何もしたくなくてグッタリとしてしまいます。消化器内科病棟では感じたことのない、尋常ではない疲れ方です。ただ横になっていたい……そのまま寝てしまうこともあります。
去年の12月、病院からいただいたボーナスが少ないことに愕然としました。コロナのために病院全体の患者数が減って、赤字が増えているというのです。私はお金には執着心はない方だと思っています。それでも今回は「こんなに働いてがんばっているのに……」と思うと、余計にめいってきました。
コロナ病棟に勤務してから時々頭をよぎるのが、「私はなぜ、看護師になったのか?」ということです。「患者に寄り添う、心も寄り添う」そんな看護を目指していたはずでした。がん患者の終末期の時も、常に患者さんの心に寄り添った看護がしたいと考えてきました。
それがコロナ病棟では、なるべく患者さんから離れて看護をしなければなりません。診察や体位を変えるために患者さんのところまで出向いた時でも、「よろしいですね」と確認してすぐに離れ、患者さんのそばに長くは居られません。患者さんから手を差し出されても、握ることはできません。主にモニターを見て、酸素濃度、血圧、心電図、呼吸数などをチェックするだけの看護なのです。現実は分かっているつもりですが、「私がやりたいと思っている看護ではない」と考えてしまいます。
コロナの患者さんが亡くなると、余計にそう感じます。あの方には何もしてあげられなかった……もっと言いたいことがあったのではないか……そう思うのです。
それでも、いまは辞められません。看護師長は毎日のように苦労して欠員の補充を考え、勤務表とにらめっこしてやりくりしています。「疲れたから何日か休みたい」なんて、みんなに迷惑になるから絶対に言えないのです。
今朝も疲れが取れないまま勤務に出てきました。それでも、重い感染防護服に着替えると、「しっかり働かなければ」という気持ちが湧いてきました。患者さんのそばに行って目と目が合った時、「この方は無事だった。生きていてくださった。データが少し良くなってきている。がんばらなきゃ」。そう思いました。
◇ ◇ ◇
Aさんから聞いたこのお話を看護師長に話したところ、看護師長は「看護師の使命感です」と言われました。体を壊さないようにAさんに休みをあげてほしい……私は心の中で祈りました。