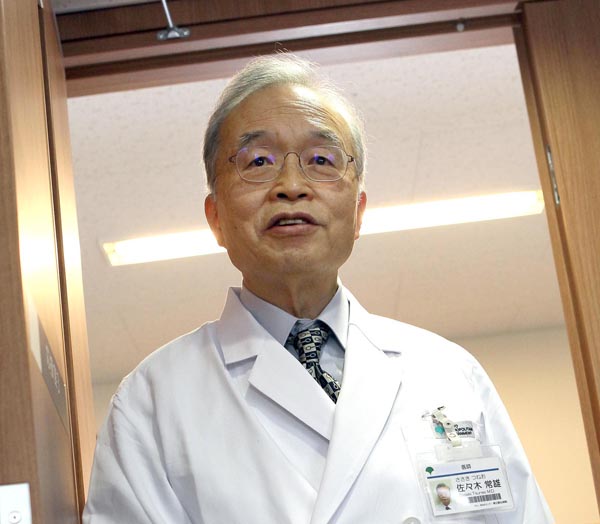先日、ある大学の医学部で講義を担当しました。いつもは学生と話し合える楽しみな90分なのですが、今回はコロナ流行のためウェブ講義となりました。残念ながら学生の反応が分からないままに、私の方で一方的に話していく形でした。
講義の題名は、医療現場の実際から医療倫理について学ぶとして、「がん診療における患者の生と死」というものです。冒頭で「この時間は、教わるとか教えるということではなく、命を、そして死を一緒に考える時間にしたいと思います」とお話しして講義を始めました。
以前は、講義が終わってからいろいろな質問を受けたり、数人の学生に囲まれての議論があったり、一昨年はその後も個人的に手紙やメールをもらったりしました。今年はそうもいきませんでしたが、それでも10日後には受講生全員から講義の感想文が送られてきました。
私の講義の主な内容は実際の臨床でのエピソードがもとになっています。
ある患者は、大学准教授だった頃にたくさんのがん患者のみとりの経験をし、開業後は地区の「死の準備教育」の講師を務めた医師でした。そのため、いざとなっても死を十分受け入れられる、自分の死においては「穏やかな死」で、恐怖を感じることなど絶対にないと確信していました。
しかし、自身が膵臓がんになり、担当医からすべてを話されて、すでに危険な状態であることを知ると彼は急に死の恐怖に襲われ、こんなことを考えたそうです。
「安楽の中で、家族にさよならを告げて、みんなに見送られて死ぬはずなのに、あの確信していたものは何だったのだろうか。死は怖くないと言い切ってきた自分はどこへ行ってしまったのだろうか?」
健康なときに考えた死と、いざ死が迫ってきたときではまったく心境が違ってきたのです。
また、2016年に起こった相模原障害者施設で元職員が入所者19人を殺害した事件のこと、難病の筋萎縮性側索硬化症(ALS)だった女性(当時51歳)に頼まれ、薬物を投与して殺害した医師2人が昨年7月に逮捕された嘱託殺人についても話しました。さらには、天寿を全うしての死、若い方のがんによる夭折といったいくつものエピソードを取り上げ、「いろいろな死を通して命の大切さを伝えたい」という思いでお話ししました。
■学生たちからの感想文を読んでみて
そんな講義の10日後に届いた学生からの感想を抜粋します。
「生きていることができている、それがどれほど価値があることなのか、心が震えました」
「心の底から死に向き合い、患者にとって支えとなったり、安らぎとなったりする言葉をかけられる医者に私はなれるだろうか。この疑問に医者になってから気づくのと、学生の間に考え始めるのとでは大きな違いがあるだろう」
「人間はどんな状況でも心のどこかで生きたいと思っている、というお考えは自分にとってはすごく新鮮でした」
「私は今まで、命や生死についてよく考えてきた。でもこの話題は重くて、友達や家族と話すことはなかなかできなかった。だから先生がいらしてみんなで命について考えた時間はとても意義深く、尊いものだと感じた」
「命についてもういちど考えることがなかったので非常にいい機会になった」
「患者さんがのみ込んだ言葉や思いをしっかりくみ取って悔しさを感じられる医師になりたいです」
「医療者は生と死を哲学し続けなければならないのだと感じました」
「『死者を思うことで、死者に心を支えてもらっている』という表現を見て、いたく感動した」
「つらい状況から誰しも逃げたくなるが、逃げ場所は死以外にもたくさんあるはずで、それを一緒に考えられる医師にならなければならないと感じた」
彼らの感想文を読んで、私は「学生たちは普段はたくさんの医学知識を学ぶことに終始しているが、むしろ彼らは人間の生と死、命を考えることに飢えていたのではないか」と感じました。
がんと向き合い生きていく
若者は人間の「生と死」を考えることに飢えているのではないか