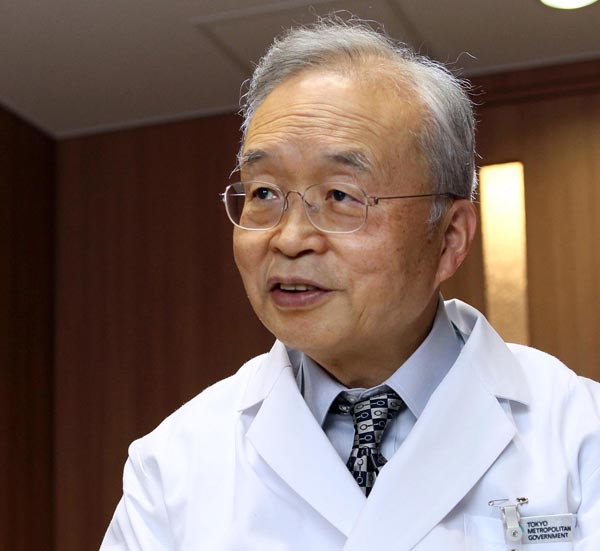約35年も前のお話です。当時23歳だったFさん(男性)は、就職した会社の2年目の健診で胸部X線に異常影を指摘され、胸部外科に来院されました。X線検査の写真では、前縦隔(心臓の前、両側肺の間)に径8センチの大きな腫瘤を認め、上大静脈を圧迫していました。
呼吸器外科医は手術不能と判断し、私が勤務している内科(化学療法科)での診療を依頼してきました。腫瘍の針生検検査では、がん細胞を認めています。
呼吸器外科医は、すでにFさんの父親に「このままでは長くは持たないと思います。覚悟をしておいてください」と告げていました。当時、この病気はいかなる治療でもほとんどが助からない時代でした。
化学療法科に転科されてきたFさんは、頚が太くなっているのが一目で分かります。私は、Fさんの父親に「がんの大きくなるスピードが速く危険な状態です。抗がん剤治療ができるギリギリと思います。何とか良くなるように頑張ってみましょう」と、治療の了解をとりました。父親は覚悟はできているようでした。
「点滴などが続くが頑張ろう」という私の言葉に、Fさんは「よろしくお願いします。先週から首や顔が腫れて苦しいです」と話されました。
■腫瘍が消えた前例があった
この前年、私は同じ「縦隔腫瘍」で若い男性2例に化学療法を行い、いずれも完全に腫瘍は消えた(5年経って再発なく完治)ことを経験していました。少なくとも私の心の中では、「こんなにがんが進んでいても勝つんだ。絶対に良くなるように頑張る」との思いがありました。
もう治療は待ったなしです。翌日からの抗がん剤治療だけではなく、大きな腫瘍が急に崩壊する時に起こる高尿酸血症など、さまざまな状況を想定して点滴などの指示を出しました。
抗がん剤の点滴を終えて3日後、やや症状が良くなってきた感じがありました。ところが、朝10時ごろ、Fさんは急に顔面が真っ青になり、呼吸困難、ショック状態となりました。昇圧剤などの緊急処置を行い、至急で撮ったX線写真では右肺が真っ白になっていました。すぐに呼吸器外科医を呼び、右胸膜にドレーンを入れたところ真っ赤な胸水が出てきました。
がんからの出血です。気管挿管、人工呼吸器装着、緊急輸血など、呼吸器外科医と一緒にヘトヘトになりながら頑張り、この時はなんとか血圧は70㎜Hgまで回復しましたが、胸膜に入れたドレーンからの出血は続きました。
そして、がんは再び大きくなり、追加の抗がん剤治療もできずにFさんは2週間後に亡くなりました。勝算あり、治せるのではないかと考えていたのに、どんなことがあっても頑張りたかったのに……残念な思いでした。
遠方から上京し、泊まり込んでいたFさんの父親は、医師から説明を受けた後にご遺体とともに淡々と帰って行かれました。やはり覚悟を決めていたのでしょう。
後日、胸部外科、放射線治療科、病理科などが集まっての合同カンファレンスがありました。標準的な治療などはない時代です。この例に対して、誰も発言はありませんでした。
Fさんが亡くなってからおよそ1カ月経って、父親が「もう一度、経過を聞いておきたい」と私を訪ねて来られました。
1時間ほどこちらの説明を聞いた後、「分かりました。自分が息子と代わってやりたかった」と漏らされました。無念でした。
私は父親と一緒にエレベーターを降りて、玄関まで見送りました。姿勢よく、毅然として去っていく後ろ姿がずっと忘れられません。
完治を目指せる白血病や悪性リンパ腫では、病状がかなり悪い状態となっても、薬が不応でなければ治すことを目標に頑張ります。Fさんのがんの場合も、状態は悪かったものの抗がん剤が効く可能性があり、実際に前の2例はがんが消えていたのです。治る可能性があったはずだと、何十年経っても心残りで思い出します。
がんと向き合い生きていく
可能性があったはず…「縦隔腫瘍」だった若者をいまも思い出す