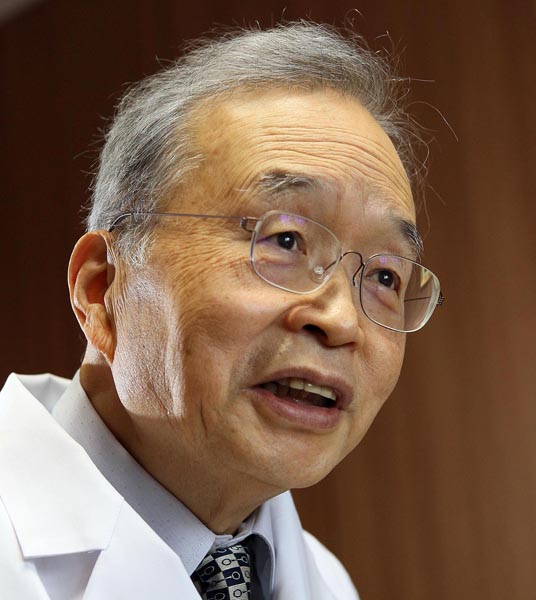がん拠点病院では、緩和ケア病棟が設置されている施設も増えていますが、多くの一般病院では「治療」も「緩和」も「看取り」も同じ病棟です。平均の入院期間が今よりもずっと長い時代のある病院でのお話です。
がんが再発し、入院を繰り返すと顔見知りになり、若い患者同士は親しくなっていきました。まだスマホもない時代ですが、退院しても病院以外の場所で連絡し合っていたようでした。
深夜、親しくなった患者同士がこっそり病室を抜け出し、階段のフロアで話し込んだりしている現場も目にしました。
特に亡くなる患者がいると、自分も短い命ではないか不安が重なって、それがさらに患者同士の親密さを増していたのかもしれません。
A君は悪性リンパ腫で、若者のがん患者仲間でも年長者でした。色黒で体格もよく、とても優しい青年でした。ギターが得意で、病室に持ち込んでいました。昼間は時々、廊下で音が出ない程度にギターを爪弾いていました。
同じ病棟のB子さんは急速に進むタイプの悪性リンパ腫でした。3回目の入院の時、B子さんは担当のD医師に言いました。
「D先生、私の家は焼き鳥屋なんだ。私が治ったらさぁ、先生、店に来て。うちの焼き鳥、うまいんだよ。においがするから病院には持ってこられないしね」
D医師は「よし、行くよ」と答えました。
しかしその後、B子さんは焼き鳥の話をしなくなりました。治療後、一時的にリンパ腫が小さくはなっても、すぐに大きくなって病状は厳しくなり、個室に移ることになったのです。
時々、A君たちがこっそりB子さんの病室を訪ね、病院のスタッフはそれを見て見ぬふりでした。2カ月後、B子さんは亡くなりました。
A君は、亡くなったB子さんの部屋に入りたいとスタッフに頼みました。結局、死後の処置(エンゼルケア)の後、A君は仲間の患者と一緒にB子さんの病室に入り、葬儀社が来るまでの間、泣きながらギターを弾きました。B子さんのご家族は、涙しながらじっと聴いていました。
その後、A君たちはB子さんのお墓参りにも行ったそうです。
■言葉にならない思いを涙目で訴えたことも
彼らは、病気が悪化していく状況で、どうしようもない苦悩をD医師や看護師に訴えることもありました。ある時は、仲間の患者が言えないことをA君が本人に代わってD医師に訴え、またある時は、言葉にならず涙目でその心境を訴えました。
同じ病気でも、再発する患者としない患者、治る患者と治らない患者がいます。病気のどこに違いがあるのか、D医師たちにも分かりません。運命としか言えませんでした。
病気が悪化していく患者と、健康な医療者とでは立場が違います。患者の話を一生懸命聞くD医師は、いつも同じ答えしか返せません。
「また良くなるから頑張ろう」
A君は入院治療を繰り返し、勤務していた会社を辞めることになりました。その1年後、A君は亡くなりました。
病院を訪れたA君の母親は「お世話になりました。ありがとうございました」と、D医師に頭を下げます。D医師は「こちらこそ。A君には、私たちもみんなもたくさんお世話になりました」と答えました。
D医師は、以前から「若い患者同士は、病気と闘う同じ戦士だった。そしてA君は仲間の若い患者たちの心の支えになっていた」と思っていました。病気と闘い、先が見えない不安を抱え、仕事を失い、なおも病気と闘い、仲間を支え、ギターを弾く……それがA君の最期の生きる姿でした。
いま、がんの診療は外来治療が中心となり、そしてがん相談支援室やがん経験者によるピアサポートも可能となっています。しかし、その利用は少ないようです。
A君は最後の入院の時だけは、病院にギターを持ち込んではいませんでした。