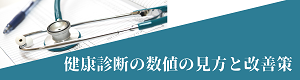右脚は外側だけ本物で、中身は太ももの真ん中からすね辺りまで筋肉を含めてすべて人工物に置き換わっています。2010年2月に受けた人工関節置換術は16時間の大手術でした。
右脚の膝関節が痛いと思い始めたのは09年の秋ごろです。近所の整形外科でレントゲンを撮っても原因がわからず、その後、鍼、電気、ヒアルロン注射など、複数の病院で複数の治療をしました。でも、すべて効果なし。そのうちに寝ていてもキシキシと痛くなり、しまいには大きなコブが膝から飛び出してきたのです。それでも、「神輿コブみたいなものだからそのうち治るよ」と言う鍼灸師に、さすがに「もうダメだ」と思い、知り合いのつてをたどって有名な大学病院を紹介してもらいました。
10年春、その病院の整形外科でレントゲンを撮ると、影っぽいものがありました。ただ、「では、MRIの専門機関で患部を撮影して、それを持って1カ月後ぐらいに来てください」と言われて帰されました。病院のMRIは緊急性がないと使えないそうです。
でも、家に帰る途中に病院から電話が入り「MRIを撮ったらすぐに病院に来てください」と言われたのです。どうやら私のレントゲン画像がたまたま整形外科の腫瘍専門の先生の目に留まって、深刻な状況の可能性が浮上したようでした。
数日後、MRIの画像を持って再び病院に行くと、細胞を採取して検査するまでもなく「悪性」と告げられ、「すぐに腫瘍を大きく取って抗がん剤治療に入ったほうがいい」という結論になりました。
「悪性繊維性組織球腫」は軟骨部のがんで悪性度が高く、5年生存率はそれほど高くありません。幸運にも翌週に手術のキャンセルが出たので、そこに予定を入れていただき、週明け火曜日に入院、水曜日に手術、木曜日から抗がん剤治療となりました。
ショックというより、ホッとした気持ちの方が大きかったです。ずっと原因がわからないまま痛い思いをしていたので……。
とはいえ命に関わる深刻な状況とは思いもしなかったので、すぐには状況がのみ込めなかったのが正直なところです。
つらかったのは「親にどう伝えるべきか」です。自分は平常心を保とうとしても、親が目の前で不安になっているとそのネガティブな空気が伝わってくる気がして、結局、言えませんでした。入院して先生の話を一緒に聞いたりする中で、おいおいわかったと思います。治療が厳しくなると不安を隠す親の気遣いが逆につらくて、「病院に来ないでください」と口にしたこともあります。
入院は8カ月間に及びました。治療の手順は、4クールの抗がん剤で腫瘍を小さくしてから人工関節置換術をし、さらに予防のための抗がん剤を4クール行うというものでした。
まずは細胞を採取して、どの薬を、どう組み合わせて使うかが検討されました。それでも1回目のクール後、肺に転移がみられました。薬を変えて2回目では肺の影が消え、その後も絶妙に組み合わせを変えながら4クールを終えて手術を受けました。そして予防の4クールを終えて、退院したのは10月。その後は半年間のリハビリとして、新しい生活に適応するための日常訓練を受けました。心身ともに大変でしたが、医療現場という別のカルチャーに触れたことは刺激的でした。あらゆるものがありがたいと思えて、感謝と愛を感じる1年間でした。
■みんなと違うことが自然に受け入れられるようになった
社会復帰をしたのは11年4月です。私は、高校生の頃からオリンピックの開会式を演出するのが夢でした。そのためのスキル、人脈、経験をずっと積んできたのです。でも、病気で来年生きているかどうかも分からなくなって、いつできるか分からない夢のために今を犠牲にすることはできないと思ったので、その時に夢は全部捨てました。
ところが、復帰後に舞い込んだある仕事で障害者やその周辺の人たちとのつながりを持ったことから、その翌年に初めてパラリンピックの開会式を見ました。「オリンピックより面白いかも」と感じて、もう一度夢を持ったのです。それが、リオパラリンピックや東京パラリンピックの開閉会式のステージアドバイザーを務めることにつながりました。
走れないし、しゃがめないし、杖で手がふさがるし、生活での不自由はもちろんあります。3カ月に1度右脚のレントゲン、半年に1度は肺のレントゲンも撮っています。加えて右脚は、10年ぐらいで中身を交換する必要があります。そうでなくても、ちょっとしたケガで細菌などに感染したら、自力で治る力がないため手術になりますから、いろいろ気を付けないといけないことが多いんです。16年春には不具合があって、一度交換手術をしているんですよ。
ただ、病気をしたことで私はすごく生きやすくなりました。以前は、自分の動きや考え方が周りと違い過ぎてとても窮屈でした。周囲に合わせなければ夢を達成できないと思ったからです。でも、杖をついて物理的に“形”が変わったら、みんなと違うことが自然に受け入れられるようになって、気持ちが自由になりました。今は、「好きな人と好きなことをして生きる」を実践しています。
(聞き手=松永詠美子)
▽栗栖良依(くりす・よしえ) 1977年、東京出身。国内外でアートや舞台、エンターテインメントを学び、「日常における非日常」をテーマに新しい価値を創造するプロジェクトを多方面で展開。病気から復帰後に、障害者の社会参加に取り組むNPO法人「スローレーベル」を立ち上げる。2016年にリオパラリンピック閉会式、21年には東京パラリンピックの開閉会式のステージアドバイザーを務めた。
■本コラム待望の書籍化!「愉快な病人たち」(講談社 税込み1540円)好評発売中!
独白 愉快な“病人”たち
悪性球腫で右脚の中身は人工物に…演出ディレクター栗栖良依さんはそれでも夢を叶えた
栗栖良依さん(演出ディレクター/46歳)=悪性繊維性組織球腫