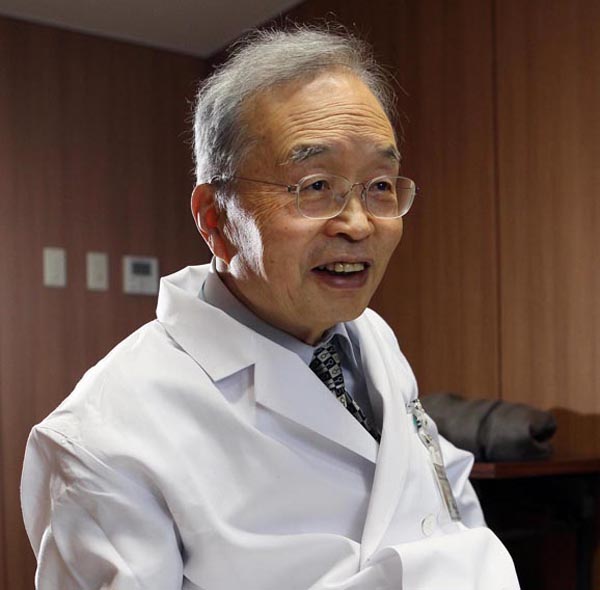「先生、お世話になりました。いろいろ相談にのっていただきまして、ありがとうございました。
夫は昨夕、亡くなりました。午後になって顎が動くようになり、しばらくしてすっと動かなくなりました。穏やかに死を迎えることができました。ここ1週間は、看護師さんが毎日来てくれました。孫にも会えました。
家に帰ったころは『治るんだ』と言っていたのですが、『こんな病気になってしまって申し訳ない』とも私に言っていました。2月か3月ごろ、もうだめかと思いましたが、今まで持ちました。訪問してくれる医師が言っていた通りでした。家に帰って、好きなものも食べました。
本人にとって、コロナで面会を制限された病院にいるよりは、家にいて、みんなに会えて、孫にも会えて、その点はずっと良かったと思っています」
電話で相談をしてきたのは、患者の奥さんからでした。
患者は70歳で、20年前に直腸がんの手術を行い、左下腹部にストーマが設置されていました。そのストーマから出血があり、背中の痛みもあって、ある病院に入院され、輸血を受けました。ストーマの部分に腫瘤ができていて、そこからの出血でした。腫瘤は直腸がんの再発ではなく、新たにできた肺がんからの転移だったそうです。肺がんは背骨にも転移していました。痛みは放射線治療とモルヒネの内服で治まり、さらに抗がん剤治療を1クール行って退院しました。
■自宅療養だからこそ笑顔もあった
1カ月後、2クール目のために入院しましたが、担当医から「体力がなく、2クール目は無理でしょう」と言われて自宅療養を勧められ、ケアマネジャーと相談の末、自宅に帰りました。
奥さんはどうなるものかと心配しましたが、本人が「帰りたい」というので、本人の意思が一番大切と思い退院を選択したそうです。緩和ケア病院にも申し込みましたが、いつ空くか分からない状況でした。
往診に来てくれる医師は週1回、看護師は2日置き、最後の1週間は毎日来てくれたといいます。
自宅療養を開始した後、だんだんと患者の食は細くなり、おかゆの量が少しずつ減っていきました。痛み止めの麻薬が効いて眠っている時間が多くなり、飲み薬は誤飲しそうになるため麻薬は貼り薬に替わりました。
部屋に運ばれた介護ベッドは電動のエアマットで、マット内部の空気が少しずつ動いて褥瘡ができないように工夫されていました。そのおかげもあってか、褥瘡もなく皮膚はきれいなままだったといいます。
週1回、息子さんと娘さんが交代で顔を見せに来て、その際にお孫さんと会えた時が、何よりうれしそうに笑顔をみせていたそうです。
一度、出張で散髪をしてもらい、ひげを剃ってもらったこともありました。さっぱりしたご主人の顔を見て、奥さんは家に帰ってよかったと思ったといいます。
亡くなる直前の2日ほどはほとんど何も口にしなくなりましたが、むせる心配もあって、水で唇を濡らす程度にとどめたそうです。
昨日の夕方に亡くなったばかりなら、今はきっとお葬式などいろいろな準備で大変だろうと思いましたが、電話での奥さんの声はとても元気そうでした。
しかし、おそらくお葬式などが終わって1週間くらいたった後、それから寂しさが湧いてくるのではないか。そのように感じました。
私はご主人を自宅で看取った奥さんにこう声をかけました。
「ご苦労さまでした。きっと奥さんにたくさん感謝していたと思います。このコロナで、入院していれば家族に会えないで、会えたとしても短時間だったかもしれません。奥さんは大変だったと思いますが、苦しそうでなかったなら、本人にとっては自宅で良かったと思います」