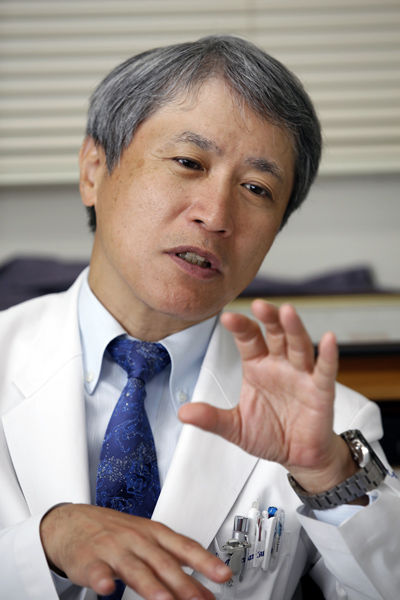Q
15年前に僧帽弁閉鎖不全症の手術を受けました。1年前あたりから再び息切れなどの自覚症状が表れ、再手術が検討されました。しかし、医師からは「前回の手術による癒着がひどく、再手術すると大出血して命に関わる危険がある」と断られました。やはり、再手術は断念したほうがいいのでしょうか。(80歳・女性)
A
私自身も含め、外科医が手術をするかどうか迷うケースはいくつかあります。まず、自分が頭に思い描いている手術をするにあたって、心臓や血管に到達するまでのアプローチに制限を受ける場合です。
いただいた質問もそうですが、再手術の患者さんの場合、前回の手術による癒着がひどく、臓器や血管が複雑にくっついてしまっているためスムーズに患部にメスを入れることができないケースは少なくありません。
また、心臓の手術をする前に食道がんの手術を受け、胸骨下、心臓の前に代用食道があるケースなども、簡単には患部に到達できません。
そうした場合、再手術でのメスを入れる場所を変える工夫をして、別方向から丁寧に癒着の剥離を進めていき、臓器損傷と不測の出血を起こさないような処理をしながら進めるなど、アプローチ法を事前にしっかり計画したうえで手術に臨みます。術前の“設計図”がより重要になってくるのです。
2つ目は、手術で心臓や血管の修復をするために必要な“材料”が制限を受ける場合です。たとえば、冠動脈バイパス手術では、患者さん自身の血管を採取してバイパスとして使用します。
内胸動脈(胸板の裏にある動脈)、右胃大網動脈(胃の周囲の動脈)、橈骨動脈(手の動脈)、大伏在静脈(脚の静脈)、下腹壁動脈(腹部の壁の動脈)などが使われますが、最初の手術のときに長持ちする健康な血管を使ってしまっていると、再手術の際に使う血管の選択が限られてしまうのです。
また、僧帽弁の閉鎖不全症や狭窄症で、自身の弁を使う弁形成術を受けている患者さんの再手術や、まだ心臓が小さい小児など、人工弁を使用できない条件が揃っていて必ず患者さん自身の組織を使って手術をしなければならない場合も手術法に悩みます。
3つ目は最近増えているケースで、全身状態が非常に衰弱している後期高齢者の患者さんです。手術自体はできるのですが、術後の全身的な回復が見込めそうもない場合は手術するかどうかをしっかり判断しなければなりません。
こうした患者さんが来院されたとき、悩んで考えた結果、「やはり手術はできない」という判断を下すこともあります。手術を終えてから回復するまでの時間と予想される健康寿命の長さ、手術をしなかった場合の自然寿命の長さを考慮し、「自然寿命のほうが長い」と予測されるようなら手術はしないほうがいいでしょう。心臓の手術が完璧に終わったなと思っても、別の病気やトラブル、回復の過程で予想もしなかった合併症が起こって死亡されるケースもあるのです。
患者さんの人生が、手術を受けたことでよりよく過ごせるようになる可能性が高ければ積極的に手術に臨みます。しかし、反対にいまより悪くなってしまう要素が多い場合は、あえて手術を選択しないという考え方もあります。
医師から「手術ができない」と告げられた患者さんは、そうした判断に基づいて出された結果かもしれません。ただし、医師の技術や病院の設備によっては、「それでも手術できる」患者さんもいます。次回、詳しくお話しします。
天皇の執刀医「心臓病はここまで治せる」
手術すべきか悩む3つのケース