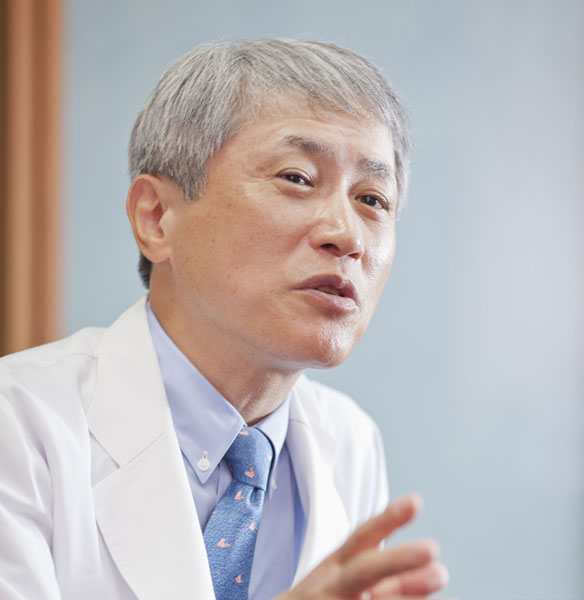信頼できない医師による、リスクの高いむちゃな治療から身を守るためには、患者さんが自分の病気の状態と、治療を選択する際のリスクをしっかり把握することが重要です。前々回から2回にわたり、そのための判断材料を紹介してきました。つまり、患者さん側もある程度の勉強が必要なのです。
自分の病気や治療に対する勉強をして、それなりの知識を蓄えている患者さんは、“出たとこ勝負”の患者さんよりも、健康な日常を取り戻せる可能性が高い印象です。これは、投資と同じようなものといえます。投資では、勉強した人は儲かる可能性がアップします。しかし、勉強もせずに他人の誘いに乗っているだけの人は、最終的には損をするケースがほとんどでしょう。
もちろん、医療は投資と違って「公共サービス」ですから、医師や病院には、リスクをはらむ“うねり”の中で患者さんが漂流したり、溺れないようにする義務があります。しかし、そうした義務を怠っている医師や病院も残念ながら存在するので、損をしないためには患者さんの勉強と知識が重要です。
また、日本では患者さんが病気や治療についてあまり勉強しない傾向が強いといえます。保険制度が行き届いているため、勉強しなくても一定水準の医療を受けることができるからです。ただ、溺れるリスクをより低くできるかどうかは、患者さんの勉強と知識にかかっています。たとえば、病院の診断機器に関する知識もそのひとつです。近年、CTやエコーなどの画像診断機器は驚くほど進化しています。心臓の検査機器でいえば、3D―CTでは、心臓の状態、弁の動き、冠動脈などを立体的にはっきり映し出すことができます。エコーも、カラー化と3次元の描写により、詳細まで判別できるようになりました。
■画像診断機器の差が予後を左右するケースも
こうした画像診断機器の進歩によって、どこからアプローチしてどの部分をどう処置すればいいかを術前にしっかりシミュレーションできるようになり、手術も進歩しました。
しかし、画像診断機器のレベルが低い病院では、検査で得られる患者さんの生体情報が変わってくるため、病気を見落としたり、病状に対して誤った判断が下される可能性もあります。
たとえば、がん治療の場合であれば、検査による細胞の悪性度の判断によって、抗がん剤を使った化学療法の内容が変わってきます。そのことで、患者さんの予後が変わってくるケースもありえます。
これが、消化器などの高分化がん(成熟した細胞ががん化したもの。正常細胞の形に近く、一般的に悪性度は低い)なら、「だいたいこれくらいの幅で化学療法をやっておけば、治療効果も延命効果もある」ということがわかっているため、予後がそれほど大きく変わってくることは少ないでしょう。しかし、未分化がん(未熟な細胞ががん化したもの。細胞の性質が確認できず、増殖、転移が速い。一般的に悪性度が高い)の場合は、最初から特別な分子標的薬を投入するなどしなければなりません。仮に診断による判断を誤ってしまえば、患者さんの予後が変わってしまう可能性もあるのです。
手術についても同じです。たとえば、小細胞肺がんの場合、最初は化学療法でがんを縮小させ、その後から手術をするというアプローチの方法があります。
しかし、最初の診断を間違えてしまったら、いきなり手術をしたことでかえってがんが散らばってしまい、予後を悪くするケースも考えられます。
画像診断機器などの検査機器のレベルが高いか低いかで、患者さんの予後が変わるケースもあり得るということを患者さんは知っておくべきです。
天皇の執刀医「心臓病はここまで治せる」
患者が“勉強”すればリスクをより減らせる