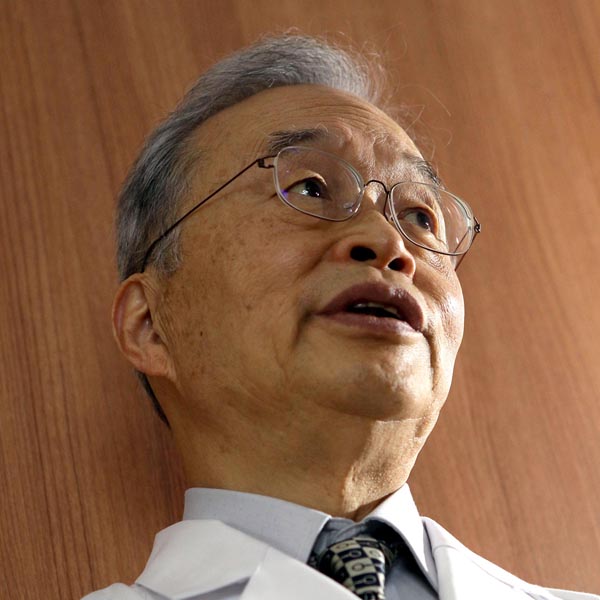「もう治療法はなく、あと3カ月の命と告げられました。セカンドオピニオンの紹介状は書いてもらいました。でも、もうあんなに冷たい病院には戻りたくありません。A先生の顔も見たくありません。この病院で治療して下さい。死んでも構いません」
15年ほど前から、私の診察室に来られるセカンドオピニオンの患者さんは、ほとんどががん専門病院からの転院を希望される“がん難民”といわれる方でした。いまでこそ少なくなりましたが、毎週、このような患者さんが訪れていました。
多くの患者さんは、保険診療ができる薬剤がまだ残っていても、治療を受けていた病院の医師から「ガイドラインに載っていない。電子カルテで決められた治療以外はできない」「もう治療法がなくなったので好きな病院に行っていい」と告げられたと言います。
セカンドオピニオンは他病院の意見を聞きにいくのであって、転院したり、担当医をかえることを目的にしたものではありません。しかし、ここで断られたらもう行き先がありません。患者さんは必死です。
こちらでお引き受けして、治療を行った患者さんはたくさんいらっしゃいます。その結果、3カ月どころではなく、長く生きられた患者さんもたくさん目にしてきました。一方で、体の状態が悪いため抗がん剤治療は無理な患者さんや、たしかにもう治療法がないと思われる患者さんもおられました。
日本におけるがん患者さんのセカンドオピニオンは、このような形で始まったように思います。担当医との関係がうまくいかなくなった患者さんも多く来られました。
「個人の尊厳、平等、最善の医療を受ける」ことは患者さんの基本的な権利ですが、さらに病気を知る権利、自己決定権、そして検証権としてのセカンドオピニオンがあります。その病院での診断は間違っていないか。勧められた治療法は妥当なのか。治療が始まる前、あるいは治療中でも他の病院での意見を聞いてみることです。他院でも診断や治療法が同じ意見であれば、より納得して治療が受けられます。また、ひょっとしたら別の治療法があるかもしれません。患者さんの多くは、「他の病院で意見を聞いてくるのは、担当医を信じていないみたいで言いづらい。気を悪くするのではないか」といった心配をされます。しかし、まったく遠慮はいらないのです。
■治療を諦めずにがんが消失した患者さんも
胃がんを患い、某国立大学病院で胃全摘の手術を受けたCさん(56歳・女性)は、手術の2年後、肝臓に転移があることがわかりました。すぐに同じ病院でシスプラチンと5―FUによる抗がん剤治療を受けましたが、効果は認められず、主治医から「抗がん剤による治療をあきらめて、緩和治療を受けてはどうか」と勧められたといいます。
そんなCさんは、私たちの病院にセカンドオピニオンのために来院されました。娘さんがインターネットで調べてくれたとのことでした。
持参されたCT写真では、肝臓の中央部に長径6センチのがんの転移を認めました。しかし、これまでの抗がん剤治療は量も期間も十分ではなく、次の治療として使える薬もまだ残されていました。そして、患者さん自身が抗がん剤による治療で闘う意思がはっきりしていることもあり、紹介元の病院の了解を得て、私たちの病院に転院して治療することになったのです。
Cさんには2カ月の抗がん剤治療を行い、下痢や食欲不振などの副作用も見られましたが、肝転移はまったく消失しました。晴れて自宅で正月を迎えることができるようになったのです。
私もうれしくて「よかったね」と声をかけると、Cさんは「神様はいたんだと本当に思いました」と喜びをあらわにされていました。初めて来院されたときの緊張した表情、退院を前にした穏やかな表情、その両方とも私には忘れられません。
がん拠点病院ではセカンドオピニオンを推進しています。自分の命がかかっているのです。患者さんの権利です。セカンドオピニオンに遠慮はいりません。
がんと向き合い生きていく
セカンドオピニオンは患者の権利 遠慮はまったく必要ない