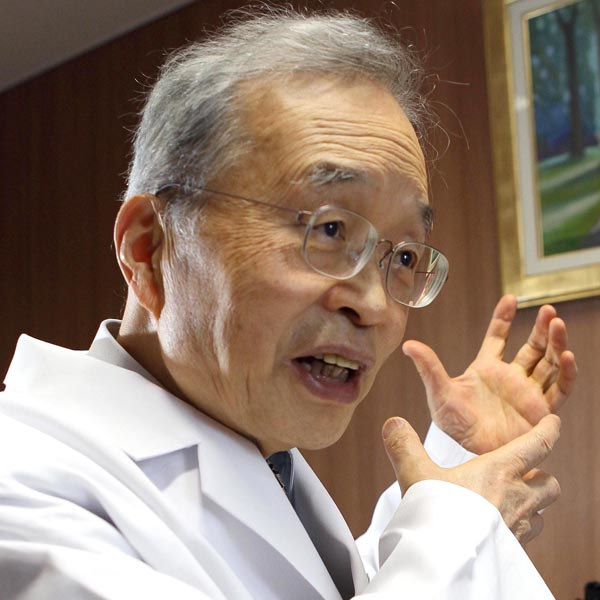鉄欠乏性貧血と低血圧があって通院中のMさん(48歳・主婦)が、急に痩せられた感じを受けました。こちらが尋ねる前に、診察室に入るとすぐにこんな話を切り出しました。
「夫(55歳・会社員)が急に亡くなって2カ月になります。突然、苦しいと言って倒れ、通院中のJ大学病院に救急車で運ばれました。肝臓がんの一部が破裂し、腹腔に出血してショック状態とのことでした。それから2日後に息を引き取りました。夫は意識がなくなっても、親戚がみんな集まるのを待っていたみたいでした」
Mさんのご主人は、13年前に胃がんで内視鏡手術、10年前には大腸がんで手術を受けたといいます。いずれも完治したのですが、7年前の人間ドックで今度は肝臓がんが見つかり、再びがんとの闘いが始まったのです。
皮膚から針を刺してがんを焼き殺すラジオ波熱凝固療法を行ったものの、新たに肝臓の別の場所にがんが出てきて、何度も治療を繰り返しました。肺に転移が来てからは分子標的薬を4年間も飲み続けたといいます。担当の医師は「こんなに長く効いた方は初めてだ」と言っていたそうです。
「ラジオ波熱凝固療法が難しくなると、担当の先生が動脈化学塞栓療法を行っている病院を紹介してくれて、そこで何回も治療を受けました。それでも、夫は決して弱音を吐くことはありませんでした。いつも前向きでしたし、生きる望みを持っていました。仕事も一生懸命に続けていて、倒れた日も出勤していました。ですから、末期的な状態とはいえ、今回はあまりにも突然のことでした」
Mさんのご主人が亡くなった後、担当医から解剖の依頼があり、「解剖によって、もし、これから同じ病気の方が同じ状態になった時には、どうすればいいかのヒントが得られます。必ず次の方の治療に役立ちます。このまま火葬してしまえば分からなくなることもたくさんあるのです」と説明されたといいます。
「担当の先生は、長い間どんなことでも相談にのってくれました。一緒に悩み、いろいろ治療法を探し、見通しは暗いのに希望を持たせてくれたのです。夫がとても信頼していた先生の役に立つのであれば、要望に応えられることができるならと思い、すぐに解剖を承諾しました」
Mさんは泣き出しそうになりながら一気に話され、それでも、最後は少し笑顔が見られました。急に夫を失ったMさんには、大変な悲しみの中でも病院や担当医に対する感謝の気持ちがあり、それがわずかでも悲しみを和らげてくれているのではないかと思いました。
■衣笠祥雄さんもそうだった
先日、「鉄人」と呼ばれた元プロ野球選手の衣笠祥雄さん(享年71)が大腸がんで亡くなられました。現役時代は、どんなにケガをしても骨折しても試合に出場し続け、「ケガの痛みよりも、休んで家でテレビを見ている方がつらいのです」と語っていた姿を思い出します。
衣笠さんのがんの状態の詳細は分かりませんが、おそらく厳しい状況になっていたのだと思われます。それでも、衣笠さんには次の試合の解説を務める予定があったと聞きます。
Mさんのご主人も衣笠さんも、がんと闘いながら亡くなる直前まで前向きに人生を生きてこられた。とても立派だったと敬服するばかりです。
ただ、がんの終末期でも前向きに生きたい、仕事をしていたいと思っていても、病状などからそのようにはできない方もいらっしゃいます。がんと最後まで闘う方、あくまで延命を求める方、治療をせずにホスピスで過ごされる方、そして死を受け入れ自宅で過ごされる方など、患者さんによってさまざまです。
東京大学名誉教授で比較文学者の亀井俊介さんが、以前、教えて下さったことを思い出します。
「ぎりぎりの状況におかれた時の生や死について、どうでなければならないといって要求するのは僭越な議論だろう。むしろ、個人の選択を温かく見守る態度をこそ、私は身につけたいと思う」
がんと向き合い生きていく
3度のがんと闘いながら亡くなる直前まで前向きに生きた