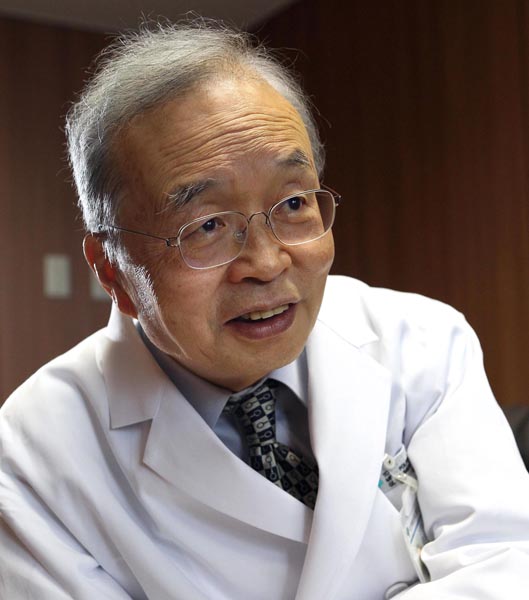「あなたはたくさんのがん患者を診てこられた。実はK先生が末期の肝臓がんで、もう治療法はないらしい。いま、心の助けが必要だと思う。本人に伝えておくから、一度、自宅に見舞ってやってくれないか」
少し前のことですが、ある先輩医師からこんなお話がありました。
K先生は大学の10年も先輩にあたり、東京の郊外で開業され、同窓会では何度かお会いしたことがありました。ただ、私はほとんど話したこともなく、少し気後れしたのですが、大変お気の毒に思って、ある日の夕方に伺うことにしました。
道すがら、どんな話をすればよいのか何も思いつかず、「とにかくお話をお聞きするしかない」と思いました。
ご自宅はひっそりとされ、ご家族はいらっしゃらないようで、ヘルパーさんと思われる方が2階に案内してくれました。50畳はあると思われる大きな和室で、床の間には大きな鎧兜が飾ってあります。薄暗い室内に布団が敷かれていて、K先生が横になっておられました。
私はK先生の枕元に座り、「先生、ごぶさたいたしております。いかがでしょうか?」と挨拶しました。K先生はうなずかれ、しわがれた低い声でゆっくりと話されました。
「よくおいで下さいました。お聞きと思いますが、肝臓がんです。痛みはないのです」
私は「痛みはないのですね」と答えましたが、その後しばらく沈黙が続きました。
薄暗くてはっきりは分かりませんが、K先生は黄疸のためか皮膚が黒ずみ、以前お会いした時よりもかなり痩せて見えます。
「だるくて……ね」
そう口にするK先生に、私は「だるいのですか」とたずねましたが、また沈黙となりました。
「選挙の時は、ここにたくさん人が集まったのです」
「そうでしたか」
そんなやりとりをしながら、私はK先生の顔をうかがったり、床の間の鎧兜を見たりしていました。K先生は「肝臓がんの治療法」や「抱えている悩み」を話されることもなく、3カ月前に医院を閉じたこと、在宅医が往診してくれることなどを淡々と話されました。
私は、K先生と鎧兜と私とがその薄暗い空間に溶け込んでいるような不思議な錯覚を覚えていました。何回も目と目が合っていましたが、不安そうにも見えません。それでも、K先生は自分の死期が迫っていることも分かっておられるのだと感じました。「何か、私にできることはありますか?」とたずねると、K先生は「いや……」と少し顔を動かされました。
1時間半ほどたって、私が「よろしければまた来ます。どうぞ呼んで下さい」と伝えると、K先生はにっこりしながら布団の中から手を出されました。私は握手して頭を下げ、立ち上がりました。
帰りの道で、私は考えました。K先生はたくさんの悩みがあったとしても話されなかった。私からもお聞きすることはしなかった。K先生のお気持ちは「自分はここにいて、つらい思いをしている。それを分かってほしい」ということだったのだろうか?
■いまもあれで良かったのかと反芻する
その1週間後、もう一度お会いすることもなくK先生は亡くなられました。
私はいまも鎧兜のある広い部屋にK先生がひとりふせておられるあの日のことを時々思い出し、いつもあれで良かったのかと反芻します。K先生は何かもっと話したいことがあったのだろうか……。
そして、K先生が別れる時に見せたあの笑顔を思い出し、「自宅に伺って良かったのだ」と身勝手に、そう思うことにしています。
鎌倉時代中期の僧で、浄土宗第三祖の良忠上人は臨死者の看護についてこう言っています。
「決してこちらから注文するようなことがあってはならない。できるかぎり、良いことも悪いことも、病人の思いにそって差し上げられるようお努めください」
800年も前に説かれたこの“あるべき姿勢”は、いまも同じではないかと思うのです。
がんと向き合い生きていく
とにかくお話を聞く…それだけで患者は笑顔を見せてくれる