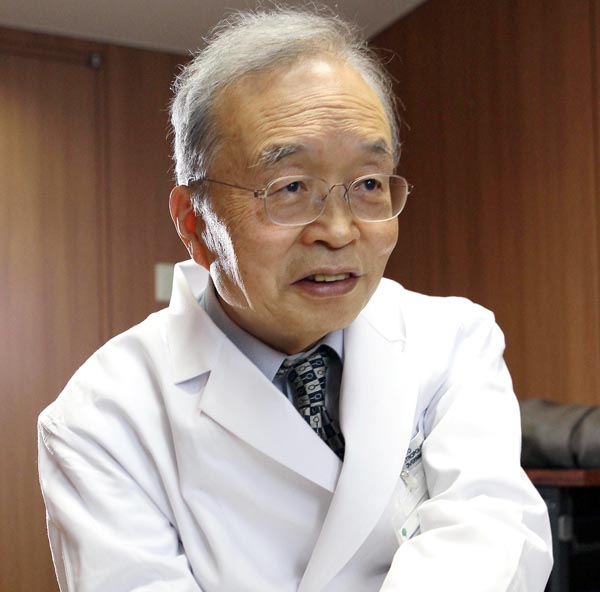主婦のGさん(56歳)は下腹部に軽い痛みと腫瘤が触れ、CTやMRIなどの検査で卵巣がんが疑われて手術となりました。担当のS医師は50歳代のベテランの医長で、Gさんには話しやすくその点は安心でした。
無事に手術は終了して7日後には退院。その10日後、Gさんとその夫のKさんにS医師から説明がありました。S医師によると「病理検査ではやはり卵巣がんでした。ステージは幸い1bと初期のもので他には進んでいません。念のためですが、抗がん剤治療で再発予防を行っておいた方がいいと思います」とのことで、Gさんは納得し、その治療を受けることになりました。
ところが、Gさんがそばにいないタイミングを見計らい、看護師から夫のKさんに声がかかりました。「旦那さんだけ診察室にお入りください」というのです。
入室したKさんは、S医師からこう告げられました。
「奥さまの卵巣がんは、組織型が『明細胞がん』といって予後が悪いタイプです。明細胞がんであることを本人に話しましょうか? どうしましょう?」
Kさんは、瞬間的に「こっそりと呼ばれたのは本人には隠した方がいいからだろう」と判断し、「それは妻には内緒にしておいてください」と返答しました。その時から、Kさんは妻のGさんには言えない秘密を持つことになったのです。
Gさんは「治療は6コース行う」と説明を受けていたのですが、ある時、「入院している同室の方は同じステージなのに、どうして私は治療回数が多いのだろう?」と首をかしげていました。またある時は「抗がん剤治療は脱毛もひどいし、手がシビれる。もう途中でやめたい」と訴えたこともありました。そんな言葉を聞くたびに、夫のKさんは胸がドキンとしました。
この話を聞いた私は、かつて乳がんと闘ったアナウンサーの田原節子さんのことを思い出しました。夫の総一朗さんは、節子さんに乳がんであることは知らせても、予後の悪い「炎症性乳がん」であることを隠していたのでしょう。節子さんの著書「がんだから上手に生きる」には、次のように書かれています。
「怒りは無力感に変わった。拍子抜けだった。半年間にわたる医師や治療方針への不満をはじめとするたくさんの疑問、不信、忿懣も、すべては総一朗の情報操作、隠蔽工作のせいだったのだ。その徹底した秘密作戦の前では、だんだん私の怒りや苛立ちも些細なことに思えてきた。それでも私は、それは離婚の理由にだってなると言った。彼は絶対言えないと言い張った。それが愛情の証のように言われると、ありがとうとまでは言わないが、つい黙ってしまうのだった。でも、このことに関しては、いまでもすべてを許してはいない」
予後の悪いタイプであることを後で知った節子さん、節子さんのことを思って隠していた総一朗さん、そんなおふたりの気持ちが、私はよく分かる、理解できる気がしました。
■今はまず本人に告げてから家族に話してよいかをき決めるが…
ところが、今のがん告知は大きく変わりました。個人情報保護法ができてからは、まず本人に真実を告げ、それから「家族にそのことを話してもよいか」を本人に尋ねるのが筋となってきたのです。家族には、本人の了解を得てから話すこと、それが普通の時代になっています。ですから、S医師はいまでは古いタイプの医師と言われるかもしれません。
しかし、たとえば悪い情報を直接、患者本人に告げた場合、患者の心が“耐えられるほど強くなっている”とは思えないこともあるのです。がんという言葉だけでもショックを受け、頭が真っ白になる方もたくさんおられます。その際、さらに「予後が悪い」という情報を伝えるのが厳しいようであれば、次回の診察以降から徐々に話すこともあります。
以前は「愛と思いやりによって、悪い情報を隠す」ことが普通でしたが、今は違います。悪い情報を患者に話す場合、「必ずあなたを支えます」というようにその患者をどう支えるかを同時に伝えることがとても大切です。
■本コラム書籍「がんと向き合い生きていく」(セブン&アイ出版)好評発売中