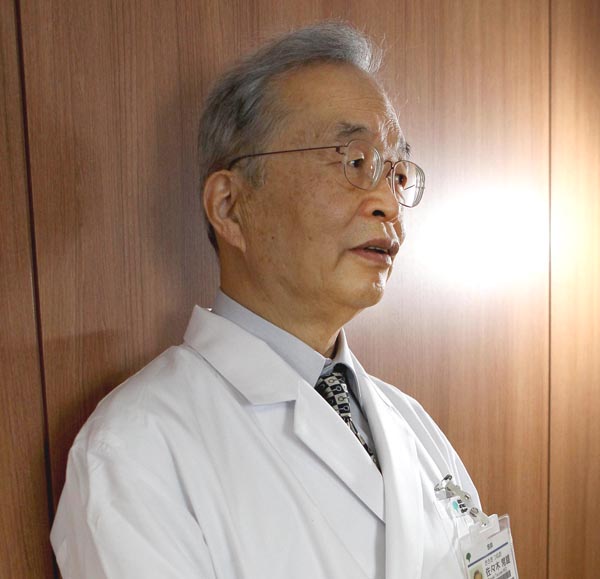がんが進行し、治療法がなくなった終末期において、多くの患者は次第に食べられなくなり、下肢の浮腫が強くなり、自分では動けなくなります。常に臥床で、安静時でも呼吸困難やせん妄などの症状から、家族も医療者もいよいよ看取りの時期が近いことを知ります。
緩和医療の医師や看護師は、患者ひとりひとりの命を考え、希望、家族の思いなどから個別に援助していきます。以前、聖路加国際病院名誉院長の日野原重明氏は、「死と、老いと、生と」という題で終末期についてこのように述べていました。
「ホスピスでは、疾患を扱うのではなしに、疾患を持って悩んでいる個人を扱う、どこまでも人間を扱うという面を強調します。患者ひとりひとりでその人の悩み方は違います。したがって、患者ひとりひとりに個別的にタッチするということが必要で、全体をまとめ、マスとして扱うことは出来ません。そういう個性的な、個別的な医療のアプローチの方法がある面では必要です」
最近、Aがん専門病院が緩和病棟を閉鎖し、コロナ病棟にしたことが報道されました。ひとりひとりの命を考えるよりも、多くの命を考える。多くの命を助けるためには、ひとりひとりの命を考えてはいられない。命を「マス」として考えざるを得ない――。コロナ蔓延の非常時には、これを容認せざるを得ないのでしょうか。
私は心配になってB病院の緩和医療の専門医に聞いてみたところ、こんな答えが返ってきました。
「今のところ、B病院の緩和病棟はコロナのために空けろとは言われていません。それでも、医師も看護師も院内コロナ病床へ、そして他院への派遣は余儀なくされています。また、10分という厳しい面会制限の中、『患者と家族の最期のタイミングは合わせたい』と思うストレスは多大で、ナースは疲弊しています」
コロナの流行からもう1年半以上も病院の面会は制限され、家族と顔を合わせるのはスマートフォンの画面だけという入院患者が多くなりました。それでも、退院できる患者はなんとかガマンできるかもしれません。しかし、看取りにおいてはどうでしょう?
面会時間の制限から、緩和病棟に勤める医師や看護師が「最期のタイミングを合わせたいと考えるストレス」は、なかなか厳しいものだと思います。命がいつ終わるのか。ぎりぎりになっても、そのタイミングは分からないことが多いのです。たくさんの患者の看取りの経験をしても、そうなのです。
■「間に合う」という事実は家族にとって大切
家族の中には、後々になっても「自分は親の死に目に会えなかった」と悔やまれる方もおられます。患者の最期を看取るために駆け付けた家族のひとりから、「今、息子がこちらに向かってもうすぐ着くのです。間に合うでしょうか?」と、たずねられたことは、何回も何回もありました。
ご臨終に間に合った、間に合わなかった。死に目に会えた、会えなかった。患者の意識がなくても、「間に合う」という事実は、家族にとってはとても大切なことなのです。
まして、がんではなくコロナに感染して、コロナ病棟で亡くなる方は患者本人も家族も悲惨です。C病院のコロナ病棟のスタッフは、「家族は濃厚接触者が多く、医師と看護師だけで見送ることが多いのです。数分だけでも最後のお別れをしてもらえたら良い方です。亡くなった方はビニールの袋に入れられて、人間扱いではないのです」と言われます。
感染が分かっても入院もできず、孤独にひとりで亡くなる方もおられます。この方に「看取り」はないのです。
毎日毎日、テレビで報道されるたくさんのコロナ感染者数、死亡者数を聞いていると、この現状が「ひとりひとりの命を考えることなく、マスとして考える社会」に変わってしまったのではないかと心配です。感染者を減らし、ひとりひとりの命最優先の人間社会を取り戻さなければなりません。