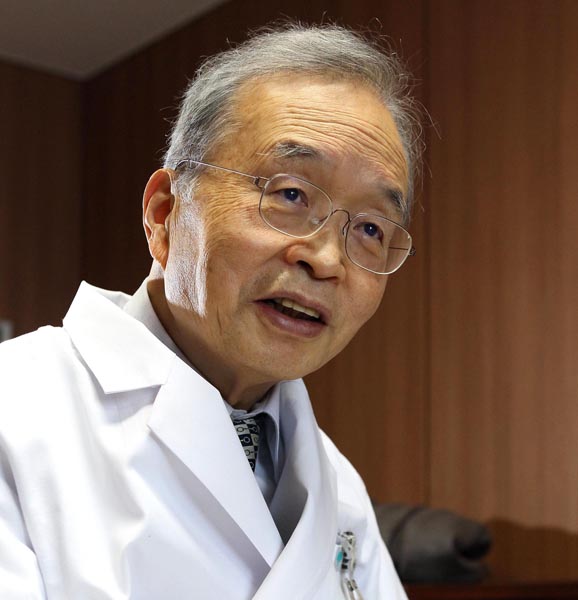先日、ある病院で行われているAI(人工知能)を搭載した胃内視鏡検査をビデオで拝見させていただきました。
内視鏡検査中、胃の中に小さな隆起が映された時、術者がAIを起動させると「がんの確率85%」と示されました。術者が気になった、あるいは異常とみた時、そこでAIを起動させるとがんの可能性の数値が「%」で示されるのです。
そこで術者が「組織診断が必要」と判断した場合は、その場所を生検することになるのだと思います。つまり、人の目とAIによるダブルチェックをして、よりがんの見逃しを少なくするというのです。
これは機械の大進歩だと思いました。将来的には、医師がAIを起動しなくても、AIの方からがんの可能性のある所を数値で示すように改良されていくそうです。
およそ50年前、私は国立がんセンター(現国立がん研究センター)の内科のレジデントでした。毎週木曜日は夕方から深夜まで病理科に詰めていました。そこでは、主に早期胃がんについてのカンファレンスが行われます。X線診断医、内視鏡医、外科医、病理医、それにたくさんの医師研修生が集まりました。
カンファレンスでは、病理医が示す胃の手術標本について、がんである根拠、がんの範囲などが明らかにされます。
「この胃には小さな潰瘍のところに早期がんがある。細い皺壁が急に太まったところ、そこは本当にがんなのか? それはX線では描出できているか? それが内視鏡ではどこに当たるか、本当のがんの範囲はどこまでか?」──といったように、ひとつの病変に対して詳細に検討されました。
全国から集まった研修生はノートを取りながら、ひと言も聞き逃すまいと熱気にあふれていました。
意見を求められた際、「ここはがんかな……」「おそらくがんです」などと発言すると、たちまち「がんかどうかはっきりしろ!」と怒られます。「この所見があるからがんです」「この皺壁はがんではありません」と、根拠を示してはっきり断言することが重要なのです。
あの当時からの知識も含め、胃がんの特徴のあらゆるデータが今のAIにはインプットされています。だから、AIを起動させるとその部位のがんの確率は○%と示すことができるわけです。
■がんの診断は「0%」か「100%」
ただ、AI検査のビデオを見て、私は少し首をかしげました。機械だから、データを集めたAIだから仕方がないのですが、その部位は「70%がん」「80%がん」などということはあり得ないのです。がんか、がんでないか、がんの診断は「0%」か「100%」でなければなりません。そのために、内視鏡専門医は日夜、プロの目、眼力を養ってきたのです。
白血病を診断する血液学でも同様です。われわれは顕微鏡をのぞき込み、患者の血液の細胞を見て、「これは白血病細胞だ」と断言してきました。「70%白血病」などという見解はあり得ません。
患者は命がかかっています。仮に、内視鏡検査が麻酔なしで行われ、患者が覚醒した状態で一緒にモニターを見ていて、「AIはがん確率45%を示し、医師は生検をしなかった」とします。すると患者は、「AIはがん45%、医師は大丈夫だと判断して生検しなかった。医師を信頼しているが、それでも私はAIでは45%がんなのだ」と考えるでしょう。この先ずっと頭の中に「45%」という数値が、その不安が残ってしまうのではないか。そう思いました。
さらに、AIが「%」を示すことで、医師がその数値に頼るようになった場合、プロの眼力が落ちてしまうのではないか? とも考えました。AIが眼力のない素人の医師に取って代わる、そのように時代は進むのかもしれません。
AIの登場はいわば産業革命です。いずれにしても、最も大切なことは見落としがなく、正確な診断がなされることだと再認識したところです。