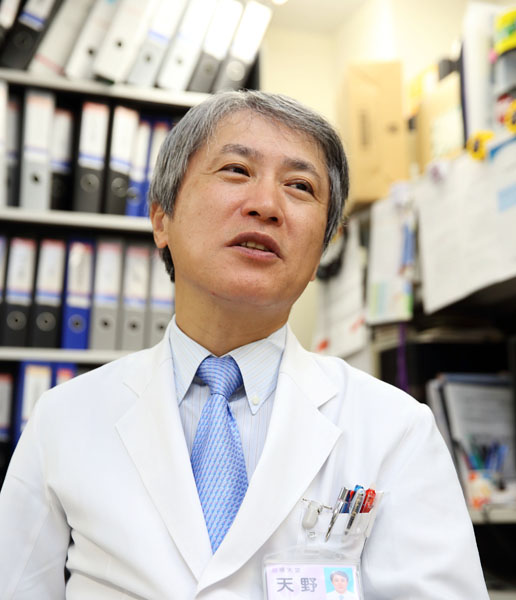今年3月、一部の抗がん剤で心臓への強い副作用が出ることを受け、日本臨床腫瘍学会や日本腫瘍循環器学会が心臓に対する副作用への対応などについて初めてガイドラインをまとめました。
乳がん、肺がん、胃がん、大腸がん、悪性リンパ腫といったさまざまながんに対する標準治療で使われている「アントラサイクリン系」の抗がん剤は、使用している患者さんの約10%で副作用として心臓の機能に障害が起こり、重い心筋症を発症して心不全につながるケースが報告されています。それらを受けてつくられた今回のガイドラインでは、心不全を予防するために超音波検査や血液検査などで心臓の状態を評価することを提案し、がん治療に伴って心血管疾患が起こるリスクが中等度以上の患者については、循環器の専門医も診察するよう推奨しています。
アントラサイクリン系の抗がん剤は心筋に対する毒性=心毒性があることが知られています。投与中も含めて短期間で不整脈、心不全、心筋症などが現れるケースもあれば、投与して1年以上、中には10~20年後になって症状が出る場合もあるので、使用する際は注意が必要な抗がん剤です。
しかも、アントラサイクリン系の心毒性によって発症した心筋症(心不全)は5年生存率が50%以下と極めて予後不良といえます。この手の心不全はなかなか見つけにくい側面があり、対応が遅れてしまうケースが少なくないからです。
アントラサイクリン系の副作用による心不全は、心臓の拡張能が落ちてくることで発症します。拡張障害の初期段階は、大学病院などの規模の大きな病院で採用されている高感度な心臓エコー装置ならすぐにわかるのですが、中小病院や循環器専門医がいないがん専門病院で使われているような装置では発見できません。病態がかなり進行して症状が現れてから見つかるケースが多いため、どうしても対応が後手後手になってしまうのです。
さらに、がんを治療中の患者さんは、抗がん剤やがんそのものの影響で貧血や低栄養を起こしている傾向があり、心不全の代償作用が崩れやすい状態になっています。代償作用というのは、心不全によって心拍出量や血圧が低下して腎血流量が減ると、交感神経系やレニン・アンジオテンシン・アルドステロン系などが活性化して心臓の収縮力や心拍数を増やし、心拍出量を維持しようとする働きです。これがうまく作用しないため、ちょっとした心機能の低下で日常生活がまったく送れないような状態の悪い心不全を招きやすいのです。
■早い段階で検査を受ける
また、アントラサイクリン系などの心毒性がある抗がん剤の治療を受けている患者さんは、「フランクスターリング曲線」でも、心臓の無理がきかず、すぐにへばってしまうことがわかっています。フランクスターリング曲線というのは、縦軸を心拍出量、横軸を前負荷(心室容積:大静脈圧)にしたとき、循環器生理学の法則に基づいてひかれる曲線のことです。たとえばクルマのエンジンは、回転数を上げるとどんどん馬力が上がりますが、ある地点に到達すると回転数を上げても効率性の低下からそれ以上では馬力が落ちていきます。心臓も同じで、脈拍が増えると心拍出量も増えていきますが、ある地点から増えなくなって心不全の状態になってしまうのです。
健康な人であれば脈拍が増えたり血圧が上がるなどして心臓にかかる負荷が大きくなってもある程度は耐えられます。しかし、心毒性のある抗がん剤の治療を受けている人は、フランクスターリング曲線のカーブが左側にきてしまって早い段階で耐えられなくなってしまいます。
そのうえ、抗がん剤治療を受けている患者さんの多くは、心臓の調子が悪くても「抗がん剤治療を受けているから」とか「自分はがんだから」などと思い込んでいるため、心臓の検査や治療がどんどん遅れてしまう傾向があります。心不全は、ある程度の高い感度の心臓エコー装置を使えば初期段階でもわかるので、診断がついてその時点で治療すれば、それほど大事に至らないケースが少なくありません。しかし、心不全の重症度を判定するNYHA心機能分類で、Ⅲ度(通常以下の身体活動《平地を歩くなど》で疲労・動悸・息切れ・胸の痛みが起こる。安静にしているときは症状がない)に入り始めたくらいのところで見逃してしまうと、突然死の危険が出てきます。ですから、抗がん剤治療を受けている患者さんで心臓の不調があれば、早い段階で検査を受けて必要な治療を受けることが重要です。
ただそれ以前に、抗がん剤治療を開始する前に心臓の状態をしっかり評価していれば、ある程度の予測は可能です。しかし、がん治療に当たる医師はがんの専門家がほとんどなので、どうしてもがんを重視して、心臓は後回しになってしまう傾向が強いといえます。
それが今回、ガイドラインにまとめられたことで、がん専門医はより心臓に注意するようになりますし、心機能に問題がないかをスクリーニングするための心臓エコー装置を高感度なタイプに変更する医療機関が増えるのは間違いありません。また、専門の検査技師や循環器内科医が必要だという要請も出てくるでしょう。
次回、抗がん剤と心不全についてさらに詳しくお話しします。
■本コラム書籍化第2弾「若さは心臓から築く」(講談社ビーシー)発売中