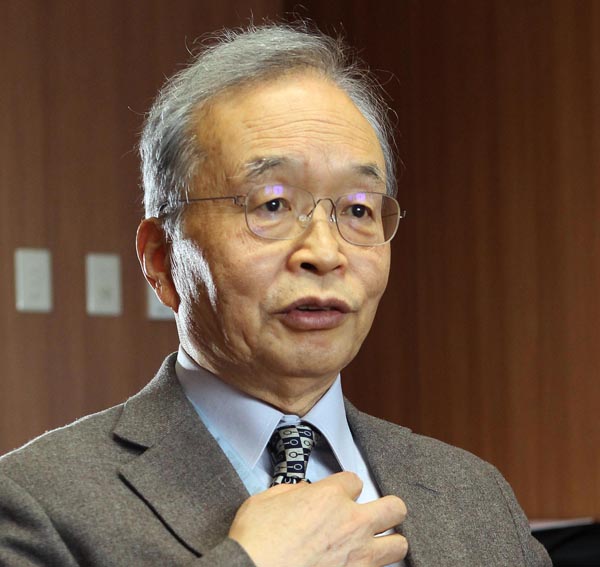知り合いの眼科医(45歳)から、「婦人科がんで治療を続けている70歳の母親の悩みを聞いてほしい」との依頼がありました。後日、母親のAさんが眼科医の息子さんと一緒にセカンドオピニオンとしてお見えになりました。
Aさんは少し下肢にむくみはあったものの、元気そうでした。ただ、2週間前に外来診察を受けた際、担当医である某がん拠点病院の婦人科部長からこう言われたというのです。
「治療を始める前から『1年の命です』とお話ししましたよね。それが2年ももったのです。薬も効かなくなったし、もういいでしょう?」
実際には、どのような雰囲気で話されたのかは分かりません。しかし、そう告げられたAさんは愕然として、「生きるのを諦めなければならないのでしょうか?」と思い悩んで相談に来られたのです。
そのがん拠点病院からの診療情報提供書を見ると、確かに、がんに対する標準治療はやり尽くされていました。この1年間は入院することなく、抗がん剤の副作用による軽度の苦痛以外は元気で過ごせたようでした。
あと1年の命と告知された患者さんが、2年生きられたからもういいだろう……そうでしょうか? 「1年の命」というのは単に過去の統計データであって、その患者さん自身に当てはまるわけではありません。
1年たっても2年たっても、過ぎてしまえばさらに生きたい気持ちになるのは当たり前のことだと思います。
過ぎた過去は過去。本人にとってはそれがリセットされて今があり、そして「これからの命」もあるのです。
ましてAさんは今はとても元気そうです。「2年もったからもういいでしょう」という言葉は、Aさんにしてみれば、自分の命は「捨てられた命」で、そう言われているのと同じことだと感じたのです。今のAさんには生きる希望が必要です。
ずっと黙っていた息子さんは、Aさんが一通り話し終わると、「2年生きられたからもういいでしょう? なんて、担当医が患者に言う言葉でしょうか」と怒りをあらわにしていました。それも当然でしょう。
■生きたいという思いを剥ぎ取ってはいけない
セカンドオピニオンが終わって部屋に帰った私は、ある大学で心理学を教えている女性教授のBさんを思い出しました。Bさんは胃がんが進行して全く食べることができなくなり、心臓の近くの血管に挿入したチューブで高濃度の栄養を投与する中心静脈栄養の袋をカバンに入れたまま私を訪ねて来られました。
Bさんは「もう治療法はなく、あと2、3カ月の命と告げられた後に本を書き上げました。この1、2カ月が人生で最も充実した期間でした」と口にした後、「これからも仕事を続けたい。だから、がんの新薬の開発状況を時々、聞きに来たい」と話されました。
私は、「メールがあるので、わざわざ来られなくても新しい治療法が出た時に連絡しますよ」と答えました。しかし、Bさんは「いえ、来ます。2、3カ月たったら、また来させて下さい」とおっしゃいます。そんなBさんを見て、私はとても強い「生きる意欲」を感じました。そして「生きたいという思い」を人から剥ぎ取ってしまうようなことは、誰もしてはならないのだと思わされました。
残り短い命を告げられて、つらい気持ちを抱えた患者さんはたくさんおられます。最後まで生きる意欲を失わない方もいらっしゃいます。
「現代人はいつまでも生きる気でいる。人間は必ず死ぬ、命に限りがあることをもっと自覚すべきだ。死を考えていないから諦めが悪い。死を受け入れなさい」
そう主張される医師もいます。しかし、がんの終末期医療においては、「最後はこうあるべきだ」と注文するのではなく、「諦めろ、諦めろ」でもなく、患者さんの思いに沿って「生きる」をどう支えるかが大切であると私は思います。
命の終わりはいつやって来るのか分かりません。そこに、命の神秘があるようにも思うのです。
標準治療法がなくなっても、担当医は患者さんと一緒に治療法を探り、一緒に悩み、一緒に次を考え、そして「自分がしっかりと支えていく」という覚悟があることを示してほしいのです。
がんと向き合い生きていく
「あと1年の命」が2年ももった。もういいでしょう? 担当医の言葉に愕然