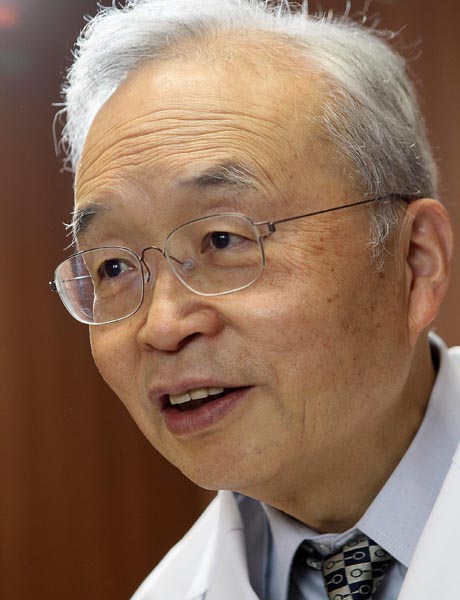22歳のAさん(男性)は微熱、リンパ節腫大、咽頭痛を訴えて私の外来を訪れました。表情は硬く、不安そうなAさんは「ボクは悪性リンパ腫です」とおっしゃいます。 診察してみると、頚部に1センチにも満たない小さいリンパ節を右に2個、左に3個認めました。しかし、これは健康な方にもみられる所見です。
Aさんは「わきの下も腫れている」と訴えますが、腋窩に触れるものはなく、胸部、腹部にも異常はありませんでした。口腔・咽頭には痛みの原因となる扁桃腺腫大や発赤などもなく、体温は36度6分と平熱でした。
念のため、採血と頚部、腋窩の超音波検査を依頼し、Aさんは検査に向かいました。結果を待っていると、Aさんに付き添ってきた母親が私に会いたいと言っていると知らされました。
さっそく面会すると、母親は一気にこう話されました。
「息子は悪性リンパ腫でしょうか? 1カ月ほど前、中学時代に仲が良かった同級生のN君が悪性リンパ腫で亡くなったとお母さんから電話がありました。N君は、大学に入ってすぐに首のリンパ節が腫れて熱があったようで、中でも悪いタイプだと診断されたようです。その後、息子はN君に2回ほど会ったらしいのですが、『頭髪はすっかりなくなって、顔は丸く膨らんでいた』と、ショックを受けていました。N君と最後に会ってから半年ほどになります。息子は浪人して2年目で、どうしてもS大学に入りたいと頑張っているんです……」
結局、Aさんの検査結果は、採血、超音波検査ともに、まったく異常ありませんでした。私はお2人に「検査では異常ありませんでした。良かったね」と言葉をかけましたが、Aさんは「本当に悪性リンパ腫はないのでしょうか?」と3回も繰り返し尋ねてきます。その都度、私が「大丈夫です。もし、心配ならまた来て下さい」と話したところ、母親はホッとされていました。
その後、来院されることはありませんでしたが、半年後に母親から「おかげさまで息子がS大学に合格した」と看護師に電話があったそうです。
■検査で異常なしと分かると症状が消える
38歳のK看護師(女性)は外科病棟に勤務していました。長年にわたって便秘症で、時々、緩下剤を飲んでいました。受診の1カ月ほど前から何度か左下腹部痛があり、便通も悪くなって、ほとんど毎日緩下剤を内服していたといいます。自分で左下腹部にしこりを触れるようになり、そこに便がたまっていると考えていたのです。
しかし、いよいよ腹痛が強くなって消化器内科を受診したところ、S字状結腸がんが見つかりました。しかし、その時はすでにがんが肝臓に多数転移していました。腸閉塞になる危険があり、がんを含めてS字状結腸切除術を受けました。肝転移に対しては動注化学療法が行われましたが、その後およそ6カ月で亡くなられました。
一緒に働いていた36歳のM医師(男性)は、K看護師が左下腹部を痛がっている場面に何回か遭遇していたそうです。K看護師が亡くなった後、M医師は自分でも不思議に思うほどK看護師と同じように左下腹部に痛みを感じるようになり、便通も悪くなったといいます。M医師は1カ月後の海外での学会を控え、発表で使用するスライドがなかなか完成せずに、イライラしていました。左下腹部の痛みの回数も増えていきました。そして、いよいよ消化器内科を受診した時は、自分もがんであると確信するほどでした。
ところが、大腸内視鏡検査を受けてみるとS字状結腸の部分はわずかな発赤だけで、がんなどの異常はありませんでした。M医師は、検査が終わった時点から、左下腹部の痛みや便通異常の症状は、まったくなくなったそうです。
このように、心の悩みが体に表れることがあります。がんを心配して来院される患者さんは、検査をしてがんでないことを証明し、それで症状がなくなることも少なくありません。
検査ではまったく異常がなく、それでも症状がなくならない場合は心療内科を紹介することもあります。心と体は深くつながっているのです。
がんと向き合い生きていく
「心の悩み」が身体にがん症状を起こす場合がある