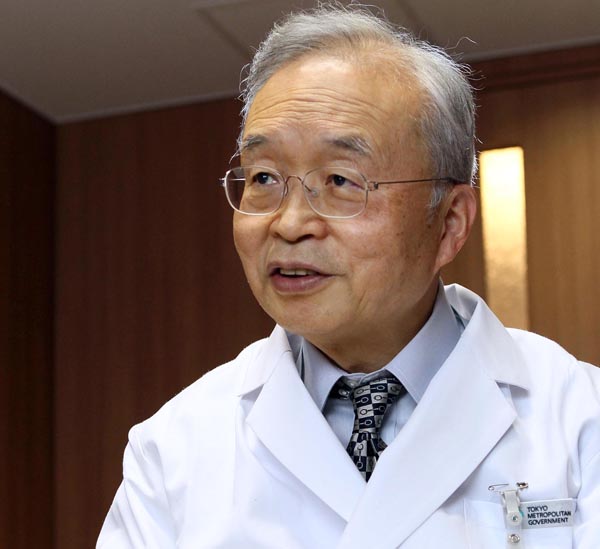つい最近、奥さまを乳がんで亡くされたAさん(67歳・男性)のお話です。
奥さまは手術を受けてから5年間、闘病を続けていました。背中に痛みがあって入院され、およそ1カ月が経過して少し痛みが治まってきたところで亡くなられました。
Aさんは、まさかこんなにあっけなく亡くなるとは考えてもいませんでした。担当医から、骨や肝臓などへの転移があることは聞いていましたが、詳しく説明されていたわけではありません。コロナ禍もあってか面会時間が制限されていて、奥さまとはそれほど話も出来ませんでした。
亡くなった後、担当医から「がんが高度に進行した状態だった」と説明されましたが、Aさんには何だか言い訳がましく聞こえました。
「それにしても、もっと看病をしてあげたかった。痛い背中をさすってあげたかった。何も出来なくとも、もっとずっと病室にいてあげたかった」
そう、Aさんは思いました。
奥さまのご遺体は病院から斎場に運ばれ、Aさん、娘、息子の3人で骨を拾いました。がんの転移があったという背骨を特に気をつけて見てみましたが、あまりよく分かりませんでした。
葬儀も3人だけの家族葬で済ませました。奥さまには姉がいますが、北海道に住んでいて来られませんでした。電話で亡くなったことを伝えた時、「コロナだから行くことができない。5年間、大変でしたね。ご苦労さまでした」とねぎらいの言葉をかけられました。
息子と娘は、3泊してそれぞれ暮らしている仙台と名古屋に帰っていきました。それからは、Aさんひとりになりました。自宅に残ったのは、机の上に置いた白い布で包まれた骨箱、遺影、斎場から持ち帰ったお花だけです。ろうそくをつけ、線香をあげ、リンを鳴らすと、チーンという音が長く響きました。
先日、奥さまの姉がまた電話をくれました。4年前に夫を亡くしており、いまはひとり暮らしです。
「Aさん、大丈夫? 落ち着いた? 行かなければと思ったんだけど、やっぱりコロナがね……」
姉の声は奥さまにそっくりで、思わず涙が出てきました。
姉は、「時間が解決してくれるから……。私なんか、夫が死んで一周忌が過ぎてから、やっとひとりに慣れてきたわよ」と言ってくれます。ただ、いまのAさんにとって「時間が解決してくれる」との言葉は、その通りだと思いながらも何だかとても冷たく響きました。「時間」と言われても、いまは一日をとても長く感じています。奥さまを見舞うため病院に通っている時は、一日が長いなどと考えたこともなかったのに……。
Aさんはゴハンを炊くのも面倒になり、コンビニで弁当を買いました。食べる前に、弁当のゴハンを少し小皿に盛って、線香の隣に供えました。
日々、声を出すことなく「時間が解決してくれる」とつぶやきながら、長い一日が過ぎていきます。
■初めて話した隣人が同郷だった
それから1カ月ほど経ったある日、故郷の同級生からサクランボが送られてきました。毎年送ってくれていて、今年も2箱でした。Aさんは数個食べれば十分で、いつもは奥さんがほとんどすべて食べていました。
「赤く輝いているこの実がこのまま悪くなってしまうのはもったいない」
そう思ったAさんは、1箱を手に隣の家を訪ねました。特に親しいわけでもなく、普段は顔を合わせた時に挨拶するだけの間柄です。
玄関のチャイムを鳴らすと、旦那さんが出てきました。
「山形のサクランボですか、ありがとうございます。私も山形の出身なんですよ。そうでしたか。私は○○高校卒業です。あなたどちらですか?」
ここに住んでからもう20年も経つのに、これが初めての会話です。結局、どこの中学校、小学校出身かという話題にまで発展しました。
同郷の人が、実は隣に住んでいたのです。Aさんは急に元気が出てきた気がしました。
「コロナが収まったら、隣の旦那さんと一緒に酒を飲みたいな」
そう思いました。
がんと向き合い生きていく
乳がんで妻を亡くし「時間が解決してくれる」と言われたが…