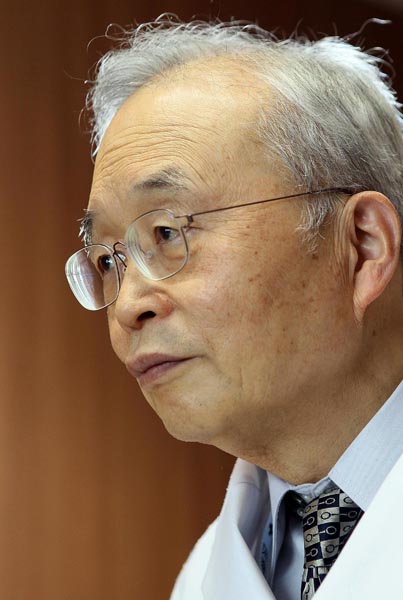Bさん(68歳・男性)は、ある病院で膵臓がんの手術を受け、退院後は消化器外来に通院しています。
この4月のことです。担当のS医師から「次回の診察は6月に予約しますが、僕は九州の方の病院に転勤することになりました。6月から担当は別の医師になります」と告げられました。
Bさんは、「はい。そうなんですか。それはとても残念です」と、その場ではあっさり答えたものの、とてもショックでだんだん不安になってきました。
「せっかくいい先生が担当してくださって、絆が出来た、安心だと思っていたのに……。私は捨てられる。いや、そんなことではない。私には別の医師が担当してくれる。それでも、その新しい医師はどんな方なのか気になる」
Bさんがいつも考えるのは、「治る確率の高いがんではなく、何でよりによって、私は膵臓がんなんかになったのだ」ということです。繰り返し、繰り返し、そう考えても仕方がないと分かっていても考えるのでした。
一方では、「コロナ流行の中でも、健診に行って良かったのだ。あそこでがんが見つかったのだから、自分は幸運だったのだ。神様が助けてくれたのかもしれない」とも考えました。また、周囲からは手術を受ける前にセカンドオピニオンを勧められましたが、S医師の説明で納得がいったうえ、コロナが蔓延する中でクラスターが出ている病院もあり、あえて他の病院に行く気にはなれませんでした。
Bさんは、3年前に健診で腹部に腫瘤があることが疑われ、胃と大腸の内視鏡検査、CT検査を行い、さらにはMRI検査とPET検査で膵臓がんが疑われ、手術となったのでした。
手術はS医師が担当してくれました。結果はやはり膵臓がんで、それでも「残さず完全に取りきれた」と言われました。
手術後は、抗がん剤の薬物治療を行いました。食事が細くなり、下痢っぽくなったこと、体重が8キロ減ったなどの影響が表れ、体の症状のことはS医師になんでも話しました。忙しいのに、たくさんの患者が待っているのに、S医師はいつも親身になって相談にのってくれ、考えていろいろな指示をしてくれました。そして、これまで再発なく過ごしてきました。ですから、BさんはS医師にとても感謝していたのです。
■定期検査が近づくと心配になる
手術を受けてから、どの新聞でも健康雑誌でも、「膵臓がん」という文字が目に留まると、すぐにそこを読むようになりました。著名人の訃報では膵臓がんの病名がよく目につきます。多くの記事では、「がんの中で膵臓がんが最も生存率が悪い、難治がん」とあり、新薬で治るようになったといったような明るい記事はなかなか見つかりません。
また、近所に住んでいる知り合いの同年代の男性が膵臓がんで亡くなったのはショックでした。先日は、息子が急に喪服姿で出かけようとしていたので、尋ねてみたら「会社の上司が膵臓がんで亡くなった」と言っていました。
Bさんは、「人は死ぬのだ。いずれはみんな死ぬのだ。だれにもやってくる、自然のことだ。そんなことは百も承知だ」と思いながら、それでも、定期検査が近づくと心配になります。人前では平気そうにしていても、ノミの心臓で、怖がりで、最近は「膵臓がん」と聞いただけでドキンとします。病気が再発したとか、問題があるとかではなく、大丈夫と思っていてもそうなのです。
さらに今回、外来担当医が代わることで不安になりました。でも、もう2年と少し再発なく過ごせれば、5年たつことになるので、完治するかもしれないのです。S医師には、感謝、感謝です。日に日に、毎日毎日、それに少しずつ近づいているはずなのです。
どうも患者同士のうわさでは、S医師は栄転のようでした。Bさんは、それを聞いてもなかなか「おめでとうございます」とは思えず、「5年たってから、転勤になればいいのに」と思うのでした。