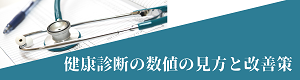ところが、蘆野さんの気持ちに反して、在宅で亡くなった患者の家族は、涙で顔をぐしゃぐしゃにしながらも満足そうな笑顔を見せた。
「患者さんの様子も、病院で亡くなるのとは違ってとても穏やかでした。入院患者には積極的な延命処置をしていたので、患者には相当な負担がかかります。点滴の青あざが細い腕にあったり、関節を動かしにくくなる拘縮や床ずれがあったりしたんです」
人間らしく人生の幕を閉じることができるのは在宅だと実感したという。そして91年には「進行したがん患者は自宅で看取る」という方針転換を行った。
「ここで大切になってくるのが“告知”です。告知がなければ、患者は『いつ治療をしてくれるんだ』という強い不安に駆られながら、闘病しなければならないのです」
患者には“知る権利”と“自己決定権”がある。今では当たり前の告知も、当時はまだ、医師の裁量によるところが大きかった。
在宅緩和医療の第一人者が考える「理想の最期」