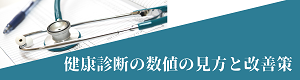1987年、蘆野さんは自宅で治療を受けられる「在宅ホスピスケア」という未開の分野に取り組み始める。当時としては全くの新しい概念で、全国5つの労災病院で試験的にスタートした在宅医療プロジェクトだった。まずは在宅で患者を診て、臨終期になってから病院に入院させ、看取(みと)りは病院で行う仕組みとしていた。
「実際にプロジェクトが始まると、それほどうまくはいきませんでした。病状が急激に悪化してそのまま自宅で亡くなるケースや、『最期は自宅で迎えたい』『もう病院には戻りたくない』といった患者や家族が後を絶たなかったのです。看取りを在宅で行うことは全く考えていませんでした」
患者が「死」を迎える時には、医療者が必ずそばにいなければならない。それが医師の最後の役割であると思っていた。だから、在宅看取りは“あってはならないこと”だった。
「患者が人生の最終段階に差し掛かっているとしても、医療者には“何とかして死を避けたい”という心理が働きます。私も当時はそう思っていたし、患者さんが亡くなると、たとえそれが寿命であったとしても、申し訳ないという気持ちになっていました」
在宅緩和医療の第一人者が考える「理想の最期」