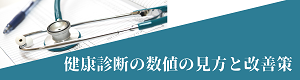小堀さんは長年、外科医として救命医療に力を注いできた。だが、訪問診療に携わるようになってから、「死なせる医療」の必要性に気づかされたという。
「医学教育を受けた医者はみな『救命・根治・延命』を第一に考えます。私が外科医をしていた時も、この3つを必要とする患者さんはたくさんいました。しかし医療に求められているのは、それだけではない。穏やかな最期を迎えるための『死なせる医療』もある。在宅医療に関わるようになって初めて、私はそれを知りました。こんな話をすると、患者も医者もみな『死は敗北』と嫌がりますが、人生の最後の医療は生かすためのものとは限らないのです」
人間誰しも、いずれは死を迎える。できれば幸せな最期を迎えたいものだが、それは「生かすための医療」が前提でないかもしれない。
97歳で独居の男性患者がいた。ひどい認知症で会話もままならない。それでも小堀さんは、ある種の友情が芽生えていると感じられた。ひっくり返した植木鉢を椅子代わりにして玄関先で小堀さんの来訪を待ち、会えば釣りの話をした。そんな付き合いが3年6カ月続いたという。
死なせる医療 訪問診療医が立ち会った人生の最期