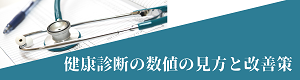「毎日の生活は充足しているように見えましたが、ある冬の朝に一変しました。看護師が訪問すると布団を掛けずに寝ていて体が冷たい。すぐに遠方に住む息子に連絡、救急搬送後に入院加療となったのです」
入院生活は穏やかなものではなかった。拘束された状態で、点滴の針は抜くし、暴れて物を投げる。息子は施設入居を希望したが、向精神薬を使用している患者は受け入れられなかった。
「そこで私が、自宅へ帰して訪問診療という選択肢もあると提案したら、担当の医師は『同じことが起きる。医者の良心に反する』と応じなかった。これは救命・根治・延命を考えた立派な答えです。しかし、ここがターニングポイントでした。それから6カ月間、彼は鎮静薬でこんこんと眠り続けて亡くなった。その半年間が彼にとって何であったか。もちろん家に帰っていたらすぐに死んだかもしれないし、もしかしたらまた私の来訪を楽しみにする生活を送っていたかもしれない。僕が言えるのは、生かす医療と死なせる医療にはターニングポイントがあり、それを意識して患者に関わらなければならないのだろうということです」
どう生きてどう死ぬか。それは患者の側にも求められている覚悟だ。
死なせる医療 訪問診療医が立ち会った人生の最期