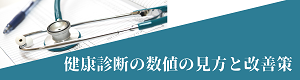「私が子供の頃は、自宅で家族に囲まれて亡くなるのが一般的でした。家族や地域の人が自宅でみとるので、一緒に暮らしている子供や孫も、死に至る過程から学びを得ることができたのです」
在宅の臨終では曖昧な時間が生まれる。家族が患者の異変に気づいて、連絡を受けた担当医が訪問し死亡確認するまでは、死亡したかどうかわからない時間が経過する。そんなどっちつかずの時間が、実は重要なのだという。
「今思い返せば、家族が死を受け入れるために必要な時が流れていたように思います。みとりを通して命の大切さを再確認する大切な儀式だったのかも知れません」
その後は次第に病院で亡くなる人の割合が多くなり、1976年には病院死が在宅死を上回るようになった。現在では全体の8割を超えている。
「死が日常から切り離され、家族を中心とするみとりが忘れ去られてしまっているのが現状です。その結果、命の尊厳を実感する機会がなくなり、家族や地域とのつながりも希薄になっていったように思います」
今求められているのは、誰にでも訪れる死・みとりを地域社会に戻すことだ。
(取材・文=稲川美穂子)
在宅緩和医療の第一人者が考える「理想の最期」